国家資格「施工管理技士」の種類は7つ【資格取得のメリットも紹介】

こちらの記事では、施工管理技士についてご紹介いたします。
この記事をお読みの方におすすめの求人
株式会社夢真が運営する求人サイト「施工管理求人サーチ」の中から、この記事をお読みの方にぴったりの「最新の求人」をご紹介します。当サイトは転職者の9割が年収UPに成功!ぜひご覧ください。
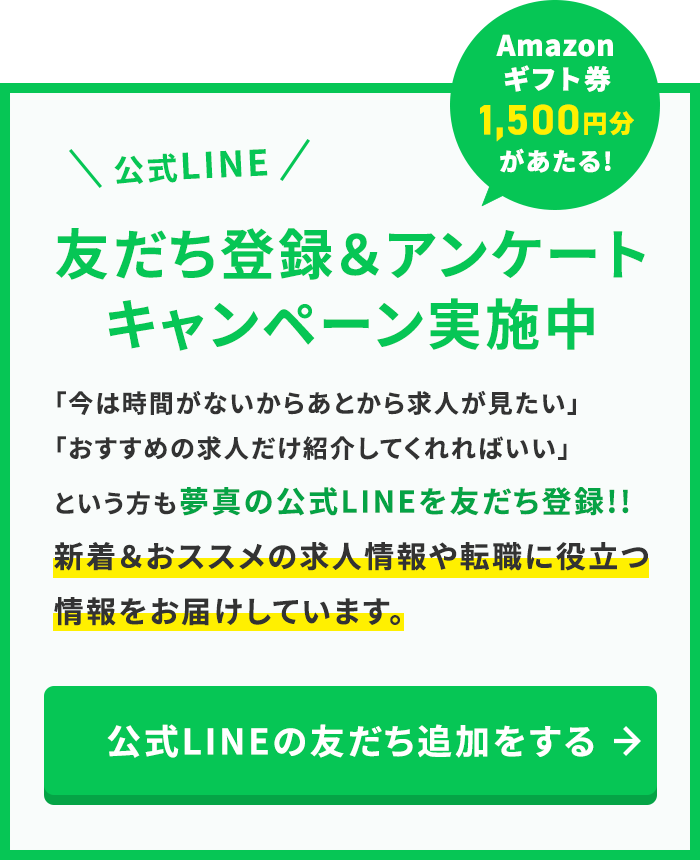
目次
施工管理技士の種類7つ
施工管理技士と一言で言っても、実は種類が分かれています。土木、建築、電気工事、管工事、造園、建設機械、電気通信工事の7種類で、電気通信工事施工管理技士は令和元年度より新設された新しい資格です。
それぞれどういった資格なのでしょうか。ここでは種類別に施工管理技士の内容についてご紹介します。
1:土木施工管理技士
土木施工管理技士とは、河川の堤防や護岸工事などの公共設備やダム、橋、トンネルなどの工事などライフラインの基盤を整備する仕事の資格です。
仕事は地域開発など公共工事がメインですが、最近では地震や台風など自然災害時の復旧工事を行うことも多いです。生活基盤を支えることが主となってきており、とても社会的貢献度が高いです。

『土木施工管理技士』の求人
土木施工管理技士の資格取得に関する記事
2:建築施工管理技士
建築施工管理技士とは、ビルなどさまざまな建物の建築現場で現場監督を行う仕事の資格です。
取得する人は、現場監督や設計事務所で仕事をしている方が多いです。建築現場には数多くの専門家が集まるため、それぞれのことを理解し、まとめる力が求められます。

『建築施工管理技士』の求人
建築施工管理技士の資格取得に関する記事
- 2級建築施工管理技士の難易度【平成26-令和5年まで】合格率・試験内容・勉強方法まで解説
- 1級建築施工管理技士の合格率【平成26-令和5年度】難易度は?試験勉強・対策方法も紹介
- 2級建築施工管理技士と1級建築施工管理技士の違いは何?試験概要を解説
3:管工事施工管理技士
管工事施工管理技士とは、その名前の通り管工事の施工を管理する仕事の資格です。
管工事とは冷暖房設備や空調設備、上下水道設備、ガス管、浄化槽などの配管工事のことを指します。
建物規模が大きくなるとともに、配管は複雑になり、配管の種類も増えていきます。ミスのない配管を行うために、詳細な施工計画や工事の工程管理が重要になります。

『管工事施工管理技士』の求人
管工事施工管理技士の資格取得に関する記事
4:造園施工管理技士
造園施工管理技士とは、造園工事の施工管理を行う仕事の資格です。公園や学校、広場、大型マンションや高層ビルの屋上緑化、道路の緑化、遊園地の造成などの工事の工程管理を行います。
造園会社などで職人としての経験を積み、資格取得を目指す方が一般的です。緑地工事や庭園工事、公園工事などの工事は時代に関わらず行われているので、そこで現場監督になれる造園施工管理技士は魅力的です。
造園施工管理技士の資格取得に関する記事
5:建設機械施工技士
建設機械施工技士は建設現場で機械の運転操作を行ったり、監理技術者や主任技術者として、現場の施工管理を行う責任者を担うための資格です。
建設工事現場で取り扱う機械は、正しい知識や技術を持っていないと扱いが難しいです。そのため安全に建設機械を操作したり、現場で確実に指示できる建設機械施工技士の設置が法律で定められています。
建設機械施工技士の資格取得に関する記事
6:電気工事施工管理技士
電気工事施工管理技士は建造物の建設などで必要な電気工事に関わる施工計画の作成や工事の工程、品質管理、電気工事の監督業などを行う資格です。
施工管理技士は施工管理上の技術責任者として重要な資格ですが、その中でも電気工事施工技士は特に業界内での需要が高く、転職の際にも非常に有利になります。

『電気工事施工管理技士』の求人
電気工事施工管理技士の資格取得に関する記事
- 電気工事施工管理技士向け転職ガイド【年収・おすすめ転職先・転職方法・メリット】
- 1級・2級電気工事施工管理技士の難易度・合格率は?受験資格・勉強方法を解説
- 1級・2級電気工事施工管理技士の平均年収や給料は?電気工事士との違いや将来性を解説!
7:電気通信工事施工管理技士
電気通信工事施工管理技士は令和元年に新設された新しい資格です。有線LANや無線LAN、防犯カメラや入退室管理システムの設備工事などの電気通信工事で専任技術者や主任技術者、監理技術者になることができます。
インターネットの普及により注目されている資格で、今後、需要が増えていくことが考えられます。
電気通信工事施工管理技士の資格取得に関する記事
施工管理技士とは
建設工事に必要な資格として建築士や施工管理技士の名前をよく聞くことがありますが、どういう資格なのかは知らないという人が多いのではないでしょうか。
施工管理技士は建設工事においてとても重要な役割を果たします。ヘルメットをかぶり現場にいるイメージがありますが、デスクワークも多いです。
この記事では施工管理技士とはどういう資格なのか、施工管理技士が求められる役割や業務内容、資格試験についてご紹介します。
施工管理技士は国家資格である
建物を建てるためには、多くの分野の専門家が必要になります。施工管理は、建設現場に関わるさまざまなスペシャリストたちをまとめ、現場で指揮することで、重要な立場です。
そんな施工管理の資格が、国土交通省管轄の国家資格である「施工管理技士」です。
現場の安全管理だけでなく工程管理や品質管理などを行う重要な業務なので、各業務の仕事内容や工程をしっかりと勉強しておく必要があります。
施工管理技士の資格等級
施工管理技士は1級と2級に分かれていて、扱える業務内容が異なります。

ゼネコンの求人、たくさんあります
業界最大級の求人数の中から、
年収にも働きやすさにもこだわった
「ゼネコン」の求人をどうぞ。
※転職成功率を上げたい人、コンサルタントに最適な求人を紹介してほしい人は2件以上の応募がおすすめです!
1級を取ると監理技術者、2級を取ると主任技術者の資格が認められます。工事の請負金額が合計4,000万円以上の場合は監理技術者が必要となるため、監理技術者になることを認められている1級である必要があります。
ただし、1級の方が2級よりも受験資格が厳しく求められる実務経験も1級の方が長いため、まずは2級から取る人が多いです。
1級建築施工管理技士資格のポイント
1級建築施工管理技士資格は、試験に合格しただけで取得できる資格ではありません。
試験に合格した後、「技術検定合格証明書」の申請手続きを行うことによって、初めて1級建築施工管理技士資格を得られることになります。
なお、合格証明書新規交付申請については、申請期限が決まっているため注意しましょう。何らかの理由で期限内に申請できず未申請のままになっている場合は、所定の再交付申請を行う必要があります。
2級建築施工管理技士資格のポイント
2級建築施工管理技士資格は「第一次・第二次検定」「第二次検定のみ」「第一次検定のみ」という3つの検定区分に分かれています。
「第一次・第二次検定」では第一次、第二次検定の両方を受験する必要があります。受験資格としては、満17歳以上で、建築工事の施工管理業務の実務経験があるという条件を満たしている人が受験できます。
また、「第二次検定のみ」は、前述の第一次、第二次の受験資格を持ち、第一次検定免除資格を有している場合に申し込みできる区分です。
そして、「第一次検定のみ」は満17歳以上であれば受験できます。さらに、合格後の有効期間内に第一次、第二次の受験資格を満たせば、「第二次検定のみ」で申し込みが行えるようになります。
施工管理技士の業務内容4つ
現場によって細かい部分では違いがあるものの、施工管理とは主に「工程管理」「品質管理」「安全管理」「原価管理」という4つを行うことです。そのため、施工管理の4大管理を行うことが施工管理技士の業務の中心だといえるでしょう。
それでは、それぞれ具体的にどのような仕事を行っているのでしょうか。
ここからは、施工管理技士の業務内容について詳しく紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
1:工程管理
工程管理とは、工期を守るために工事全体のスケジュールを把握し、作業ごとの日程調整や工事の進め方などを調整する仕事です。具体的には、工程表を作成し、工程表と実際の工事の進捗を確認しながら、予定とズレが発生しないようにスケジュール調整を行います。
工事には非常に多くの作業があり、それぞれの工程で多くの職人が関わることになります。このような工事を、無駄なく進めて行けるようにすることが工程管理の仕事です。
2:品質管理
品質管理とは、設計図どおりの品質を満たすために行われている業務です。
デザインや強度、寸法、材質、機能などが仕様どおりの品質を満たしているか、品質評価の対象となる項目ごとに定められている方法で品質試験を行い、品質のチェックを行いながら各工程を進めていきます。
また、品質管理では品質を証明するために、現場の写真を含めた施工記録を証拠の書類として残すことになります。
3:安全管理
安全管理とは、安全な建設現場の作業環境を整えるために行われている業務です。
建設工事には多くの作業工程があり、工程ごとに多くの職人が関わることになります。そのような現場ですべての作業員が安全に作業ができるように、機材点検や工程の確認作業、作業員の健康チェックなどを行います。
また、ヒヤリハット事例を現場で報告し、周知を行うとともに改善方法を立てることも安全管理の1つです。
4:原価管理
原価管理とは、会社の利益を確保するために行われている業務です。工事にかかる資材や人件費、建設機械などの原価計算を行い、予算を超過しないように工事の費用を管理します。
また、工事ではできるだけ費用を抑えることが求められるため、無駄のない人員の配置や、機械のレンタル費用などを検討するなどして、工事の進捗に応じたコストダウンを行う必要があります。
施工管理技士の資格を取得するメリット4つ
さまざまな工事現場で重要な役割を果たす施工管理技士ですが、資格を取得するとどのようなメリットがあるでしょうか。
資格を取るためには受験勉強など準備が必要になりますが、取得することで現場で責任者になれたり転職上有利であったりします。ここでは、施工管理技士の資格を取得することで得られるメリットを4つご紹介します。
1:専任の技術者になれる
施工管理技士は建設業者の営業所で専任の技術者になることができます。1級であれば特定建設業と一般建設業の両方で、2級であれば一般建設業で専任の技術者になれます。
特定建設業または一般建設業の許可を受けている建設業者は営業所ごとに必ず専任の技術者を配置することが建設業法で義務付けられています。施工管理技士などの有資格者がいないと建設業許可を維持できなくなるので建設業者にとっては常に必要な人材と言えます。
2:建設現場の監理・主任技術者になれる
建設現場には監理技術者または主任技術者を設置することが法律上義務付けられています。請負金額の総額が4,000万円を超える工事であれば監理技術者、それ以外は主任技術者の設置が必要です。
1級施工管理技士の資格保持者は監理技術者、2級施工管理技士の資格保持者は主任技術者として認められます。
また、法律上の問題だけでなく監理・主任技術者としての管理能力があると証明できるので、年収アップにも繋がります。
3:転職・キャリアアップしやすくなる
施工管理技士の資格を取ると、転職でもキャリアアップでも有利になります。
施工管理技士の資格保持者は工事現場で常に必要です。年齢が高くなると転職が難しいことも多いですが、施工管理技士の資格があると50代でも建設業界で引く手あまたな状態です。
施工管理技士を取ると工事現場で重要な立場につくこともできます。また、1級施工管理技士の資格取得によって監理技術者など新たな資格にもチャレンジできます。
4:業務の幅が広がる
施工管理とは、施工の計画をはじめとして現場での工程管理や品質管理、足場点検などの安全管理など幅広く業務を担う仕事です。コミュニケーション能力や問題解決能力も求められます。
施工管理技士の資格を取得するということは、これらの幅広い業務を行えると認められることになり、実際にその業務を担うことになります。
施工管理技士に必要とされる3つのスキル
施工管理の仕事は工事全体のスケジュール管理を行い、品質を落とさずに安全に、納期までに工事を完了させることです。そのため、施工管理技士は日々幅広い業務を行う必要があり、それだけ求められるスキルも高くなります。
それでは、施工管理技士にはどのようなスキルが求められるのでしょうか。ここでは施工管理技士に必要とされる3つのスキルを紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
1:コミュニケーション能力
建設工事では、さまざまな工程に携わる職人が協力して1つの目標へ向かって仕事をすることになります。
すべてのスタッフが1つのチームとしてスムーズに仕事ができるようにするためには、施工管理は上司とも部下ともしっかりとしたコミュニケーションを取り、信頼関係を構築する必要があります。
施工管理技士がコミュニケーションによって現場をまとめれば、チーム全体で協力して作業をスムーズに進められるようになるでしょう。
2:統率力
施工管理技士は現場を統括してまとめ上げる立場にあるため、高い統率力が求められます。
たとえば、建設現場ではさまざまな年齢層のスタッフが一緒になって仕事を行うため、中には施工管理技士よりも年齢が高く頑固な職人もいます。
そういった職人を含めて周りに敬意を払い、モチベーションを下げることなくチームのパフォーマンスを最大化することは施工管理技士の仕事です。
また、リーダーシップを取ってチームを牽引することも大切です。
3:マネジメントスキル
施工管理技士は工事の進捗管理を行う立場の人間であるため、プロジェクト全体を把握し、管理するマネジメント能力が求められます。
工事の進捗に応じて関わるスタッフや業者、作業内容などを把握し、適切な作業を割り当てる必要があります。
また、資材搬入の時間なども把握し、工事全体の進捗を見ながら、その日一日の作業が適切に完了できるようにコントロールするのも施工管理技士の仕事です。
施工管理技士が必要とされる理由
プロジェクト全体を統括する施工管理技士は、建設現場では欠かせない人材となっています。そのため、企業の中には施工管理技士の資格取得者に手当を出しているケースも多く見られます。
それでは、施工管理技士が必要とされることには具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは施工管理技士が必要とされる理由を企業サイド、現場サイドそれぞれでご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
企業サイド
企業サイドのメリットとしては、現場に配置することが義務付けられている専任の技術者として、施工管理技士を配置できるようになります。専任の技術者を置くことは必須のため、施工管理技士がいなければ建設業許可を取得することもできなくなります。
また、施工管理技士は経営事項審査の技術力評価で1人5点加算されるため、企業サイドとしては、非常にニーズが高い人材となっています。
現場サイド
現場サイドのメリットとしては、不足している監理技術者が確保できるというメリットがあります。
施工管理技士は監理技術者として建設現場を統括するキーマンとなっていますが、現在は監理技術者も高齢化しており、どこの現場でも不足しているのが実情です。
そのため、施工管理技士になれば現場や業界での自身の価値をアップさせられるため、転職でも有利になるといえるでしょう。
施工管理技士の試験を受けるときのポイント4つ
施工管理技士の試験を受けるにはどのようにすればよいでしょうか。
施工管理技士の試験は年に1回、東京・新潟・名古屋・大阪・広島など全国の試験会場で行われます。令和2年(2020年)度についてはコロナ禍の影響により技術検定が一部中止になったり試験日延期になったりしましたが、次回以降に向けてぜひ試験のポイントを押さえておきましょう。
ここでは、施工管理技士の資格試験を受けるためのポイントを4つご紹介します。
1:実務経験が必要
まず、施工管理技士試験を受けるには、一定の実務経験が必要です。
1級施工管理技士の場合で大学の指定学科を卒業後最短で3年以上の実務経験が必要で、専門学校卒や指定の学科以外であるとさらに長い実務経験が必要になります。2級の場合で、大学の指定学科を卒業後1年以上の実務経験が必要になります。
実務経験年数は厳正にチェックされます。卒業証明書などで経歴詐称が発覚すると受験停止になったり資格を剥奪されます。
出典:令和3年度 1級 建築施工管理技術検定のご案内|一般財団法人 建設業復興基金
2:1級と2級で試験の内容が異なる
施工管理技士は資格取得後、1級と2級で対応できる工事の規模などが異なりますが、試験内容も異なります。
いずれもマークシート式の学科試験と実地試験の両方に合格する必要があり、実地試験だけ合格できなかった場合、翌年であれば実地試験だけ受けることも可能です。また、1級建築士の資格がある人は、学科試験は免除されます。
なお、2級から順番に受けていく必要はなく、ご自身の業務経験などに応じて選ぶことができます。
3:令和3年度から試験制度が変更される
現在、学科試験と実地試験の両方に合格することで資格が取得できる施工管理技士ですが、内容改正があり令和3年(2021年)度より第一次検定と第二次検定という名前に変わります。
この変更により、第一次検定を合格しただけでも施工管理の基礎技術を理解している技士補という資格が得られるようになります。これにより技士補が工事現場の監理技術者の補佐を行えるようになり、監理技術者は複数の現場の兼任が可能になります。
4:施工管理技士の難易度
施工管理技士の試験の難易度はどのくらいでしょうか。1級は出題範囲が広く、合格率が40%前後と半数以上は受からないので簡単ではないことがわかります。2級は学科試験は合格率が50%前後です。
資格取得のために総合資格学院や日建学院などのスクールに通う方も多いです。また、ユーキャンなどの通信講座でも勉強することができます。
なお、試験の詳細は一般財団法人 建設業復興基金のWebで確認できます。
施工管理技士の資格を取ってキャリアアップを目指そう
施工管理技士の資格取得メリットや試験におけるポイントなどをご紹介してきました。施工管理技士は1度取得すれば講習だけで更新ができる資格で、工事現場でリーダーとして活躍することができ、また自身の業務も幅が広がります。
施工管理技士の資格保持者は、建設企業にとっても常に必要な戦力です。最近は女性の合格者や受験人数も増えました。キャリアアップや転職先を探すのにも有利な資格なので、今すぐ学習を始めましょう。
この記事をお読みの方におすすめの求人
株式会社夢真が運営する求人サイト「施工管理求人サーチ」の中から、この記事をお読みの方にぴったりの「最新の求人」をご紹介します。当サイトは転職者の9割が年収UPに成功!ぜひご覧ください。

当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。
おすすめ求人

編集部
建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。
株式会社夢真 コーポレートサイト

































