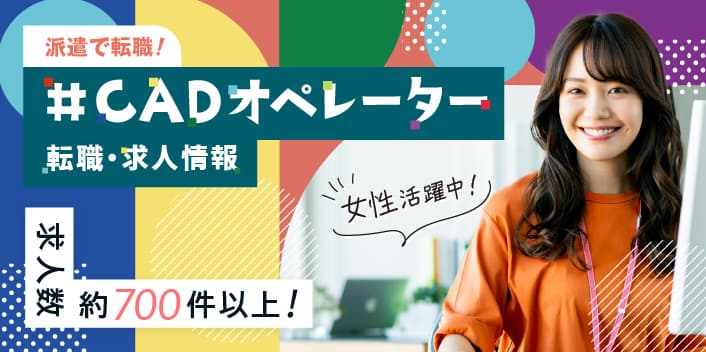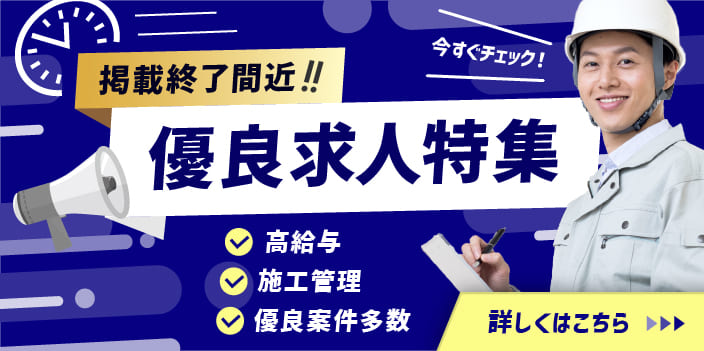土木業界の現状と将来性を解説|今必要とされる業界に参入するメリット


最短30秒で予約!転職のプロに相談しよう
今よりもっと良い条件で働きたい方は当サイトにお任せください!
目次
土木業界とは?
土木(工事)業界とは、私たちの生活を支える道路やトンネル、鉄道、空港、あるいはダムなどのインフラ整備、また災害時の復旧工事や街づくりに携わる工事を担う業界のことをいいます。
多様な工程を持つ土木工事が基本であるため、土木業界では様々な業種の会社が同時に関わることが一般的となっています。
インフラ整備における土木業界の重要性
土木業界によるインフラ整備にはフロー効果とストック効果と呼ばれるものがあり、フロー効果は、道路工事や鉄道工事、治水工事、上下水道工事などの公共投資事業によって生産、雇用や消費の経済活動が派生的に創出され、短期的に経済全体を拡大させることとされています。
一方でストック効果とは、整備された社会基盤・資本が機能することによって、継続的に中長期に渡って得られる効果のことをいいます。またストック効果には、安心・安全効果、生活の質の向上効果、生産性の向上効果といった社会ベースの生産性を高める効果もあります。
つまり、土木業界によるインフラ整備の効果や役割とは、私たちの社会基盤・資本を機能させ、それらが機能することによって、経済活動の創出、生活環境や質の向上にもつながるものといえます。
土木業界の取引の流れ
土木業界の取引の流れは業界の独特な構造上、受注方式のビジネスを取っています。また、公共事業と民間事業で取引の流れは大きく異なります。
公共事業では、従来から入札制度が採用され、工事の種類によって公募型指名競争、工事希望型指名競争、技術提案型競争などがあります。また、工事を発注する際には最初に資格審査が行われ、建設業許可取得の有無や経営事項審査などの審査を受ける必要があります。
一方、民間事業では、大まかに6つのステップで取引が行われています。設計業者の選定、次に設計監理業者による設計・積算業務、見積もり依頼業者の選定、見積もり、設計監理会社・候補企業との協議や交渉、そして契約・受発注となります。
土木業界における工事の8つの種類
土木業界は、インフラ整備に携わる仕事が主となっています。
まずインフラとは、infrastructure(インフラストラクチャー)から来ており、「下部構造」などを指す用語になります。そして、インフラ整備とは主に道路や水道、空港、河川などの生活を支える上で非常に重要なものを整備する仕事です。
以下では、橋梁工事やダム工事など8つの工事について紹介していきます。
- 1:橋梁工事
- 2:ダム工事
- 3:水道関連工事
- 4:道路工事
- 5:トンネル工事
- 6:空港建設工事
- 7:河川工事
- 8:土地区画整理
1:橋梁工事
橋梁(きょうりょう)工事は、河川、谷、そして海とで分けられてしまった地域を橋でつなぐことによって人や車などの移動を可能にし、地域社会や産業活動を支えています。
橋梁工事には複数の種類があり、PC(プレストレストコンクリート)橋梁工事、PCロックシェード橋梁工事、コンクリート構造物での橋台工事、そして橋脚工事に分類されています。
たとえば、PC橋梁工事とは、予め計画的にコンクリートに圧縮力を与え、荷重による引張応力を打ち消し、耐久力を向上させた鋼材を使用し、橋梁を造る工事のことをいいます。
2:ダム工事
台風や豪雨などによる水害や土砂災害、空梅雨による水不足などの自然災害を防ぐために、ダム工事は大きな役割を担っています。ダム工事には、ダム建設工事、砂防ダム工事、貯水池ダム工事の3つがあります。
砂防ダム工事は、山間などで発生した土石流の流れを阻止したい場合に行われます。この工事では、上流から流れてくる土砂を一度受け止めるためのポケットを造り、下流に流れる土砂の量を調節できるようにします。
3:水道関連工事
土木工事には、私たちが普段から利用し欠かすことができない水道に関する工事も含まれています。水道関連工事には公道下等の下水道の配管工事、下水処理場自体の敷地造成工事、公道下等の上水道管埋設工事、そして一般水道工事の内の開削工事と小口径推進工事があります。
4:道路工事
人や車が移動する際に使う道路は、歩行や走行のしやすさだけでなく、街の美観に対しても影響があります。
道路工事には、道路改良工事、道路修繕工事、道路構造物工事、道路開設工事があります。道路改良工事は、道路を使いやすいように整備する工事を指しており、たとえば段差をなくすなどのバリアフリー化や狭い道、見通しの悪い道など改良する工事のことをいいます。
また、道路修繕工事とは、老朽化した道路のメンテナンスや標識やガードレールなどの交換する工事のことをいいます。
5:トンネル工事
トンネル工事の標準的な工法は、シールド工法、TBM(トンネル・ボーリング・マシン)工法、山岳工法の3つです。
シールド工法とは、シールド機や様々な機器を使用してトンネルを掘った直後に、トンネルの壁をセグメントを用いて造る工法をいいます。砂や粘土、岩盤など様々な地質でトンネルを造るため、地下水が豊富にある場所でも安全にトンネルを造ることが可能です。
TBM工法は、岩盤などの堅い地盤を掘削できるTBMと呼ばれる機械を用いるため、山地部にトンネルを造ることが得意な工法です。また、シールド工法と同じようにTBMでトンネルを掘った直後から、トンネルの壁をセグメントを用いて造ります。
山岳工法は、直接岩盤などを機械や人力などで掘りトンネルを造る工法です。直接、地盤を掘り進めていくため、地質の変化や障害物の発生などに対応しやすくなっています。
6:空港建設工事
空の玄関ともいわれる空港の建設工事も土木工事の1つです。空港建設工事は、まず用地測量と設計を行ない、海上の空港か陸上の空港かで工事の内容が変わります。
海上に建てる場合には護岸工事と埋立造成工事を行い、陸地に建てる場合には用地造成工事を経て舗装工事や建築工事を行います。
7:河川工事
令和2年4月30日時点の国土交通省の調査によると、日本には河川法の適用または準用を受けた河川で、約35000以上あります。こうした多くの河川による水害を防ぐために、河川工事が行われています。
河川工事には、河川を整備する河川工事、河川改修工事、河川構造物工事があります。また、海岸工事と呼ばれる工事も含まれており、水底の土砂などを取り除き(浚渫工事)ます。

ゼネコンの求人、たくさんあります
業界最大級の求人数の中から、
年収にも働きやすさにもこだわった
「ゼネコン」の求人をどうぞ。
※転職成功率を上げたい人、コンサルタントに最適な求人を紹介してほしい人は2件以上の応募がおすすめです!
8:土地区画整理
土地区画整理工事には、土地区画整理工事、土地造成工事、大規模な宅地造成工事の3つがあります。特に土地区画整理工事は、道路や公園、下水道などの街づくりに関わるため、その地域で暮らす人たちの生活環境の改善に役立つこと工事といえます。
土木業界の3つの将来性

土木業界は、その役割から、私たちの生活を支える縁の下の力持ちのような存在で、社会における重要性は非常に高いといえるでしょう。
そんな土木業界がこれからも必要とされ続けるのか、また最新技術との向き合い方など、土木業界の将来性について説明していきます。
これを参考に、土木業界の将来をぜひ一緒に考えてみましょう。
- 1:土木業界はこれからも常に必要とされる仕事
- 2:ICT・AIを活用した最新技術の導入
- 3:防災関連の工事が今後も増加
1:土木業界はこれからも常に必要とされる仕事
土木業界はインフラ整備に加え、災害発生時の復旧や復興にも欠かせない業界であるため、近年の業界規模や売上高は、堅調な推移を見せています。
東日本大震災以降は、熊本や北海道地震、台風や集中豪雨による水害など自然災害が相次いで発生しているため、復旧・復興工事が増加しています。
また、東京オリンピック・パラリンピックに伴う都心の再開発に加え、大阪万博やリニア新幹線の開業予定といったインフラ整備も加速しています。
大規模なインフラ整備だけでなく、高度成長期に整備されていった様々なインフラの老朽化への改修需要も拡大しています。こうした需要を背景にし、将来性のある土木業界といえるでしょう。
2:ICT・AIを活用した最新技術の導入
土木業界では慢性的な人材不足に加え、若手入職者の不足、さらに高齢者の大量引退が控えているため担い手の確保が喫緊の課題です。
国土交通省ではでICT等を活用した「i-Construction」を推し進めており、全ての建設生産プロセスにおいてICT等の技術を導入し、生産性の向上を目指しています。
また、民間でも省人化を目指しており、AIを活用したシステム開発が行われています。ICT・AIを活用することで、土木業界の将来性を高めていくことを目指しています。
3:防災関連の工事が今後も増加
日本は国土を構成する大陸プレートによって地震が起きやすい国です。近年では東日本大震災、熊本や北海道での地震が記憶に新しいでしょう。
大規模な震災発生は今後も懸念されており、特に南海トラフ地震や首都直下型地震の可能性が心配されています。国土交通省は国土強靭化基本計画を策定し、巨大災害に対する取り組みを実施しています。
土木業界は、こうした災害に対する公共インフラ整備に携わっているため、今後も防災関連の工事受注が増加すると予測されています。そのため、将来性の高い業界といえるでしょう。
土木業界の課題
土木業界は将来性を持ちつつも、長い間問題になったままの課題もあります。
他の業界に比べて女性の入職者が少ないことや、少子高齢化のあおりを受けた人手不足といった課題に悩まされており、様々な施策を行ってきました。
ここからは土木業界が抱える課題とその取り組みについて紹介していきます。
- 女性にとって働きやすい環境づくり
- 人手不足の解消
女性にとって働きやすい環境づくり
近年の多角的視点によるダイバーシティ化の必要性などによって、土木業界においても女性の入職者を増やすことが求められはじめています。
平成26年8月に、国土交通省と建設5団体によって「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」が策定され、土木業界・建設業界で女性が働きやすい環境や制度の整備、女性の入職や活躍を目指した様々な取り組みが行われています。
たとえば、一般社団法人日本建設業連合会では、女性が働きやすい現場環境づくりや整備を目指し、現場環境整備マニュアルやチェックリストを策定しています。
具体的な取り組みとして、女性専用トイレや男女使用可能なシャワー室の設置、使用する工具・器具類の軽量化などがあります。
出典:「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」 |国土交通省、(一社)日本建設業連合 会 他4団体
人手不足の解消
土木・建設業界は慢性的な人手不足の現状があり、1997年の685万人をピークに減少傾向にあります。さらに追い打ちをかけるように、数年後には業界を支えている高齢者の大量離職(引退)が予想されており、人手不足の解消は喫緊の課題となっています。
そのため、国土交通省による建設業働き方改革加速化プログラムが策定され、働き方改革による担い手の拡充、ICT・AIを活用した最新技術の導入による省人化(生産性向上)への取り組みなどが行われはじめています。
土木業界の魅力
土木業界の将来性や課題について説明してきましたが、土木業界の魅力について説明して行きます。
土木業界が持つ魅力に、仕事の成果が目に見える形となることや、オリンピックや万博といった国の大きなイベントに関われること、災害の脅威から住民を守ることなどが挙げられます。
1つの工事が完了した際には、達成感を感じやすい業界ともいえるでしょう。
新型コロナウイルス感染症による土木業界への影響
新型コロナウイルスは飲食業や観光業をはじめ、様々な業界に影響を与えました。土木業界全体の最新の収支では、影響が出ている業界と比較すると顕著なものとなっていません。
その理由は土木業界が担う役割にあります。土木業界は、私たちの生活や産業、さらに防災面でも都市機能を支えるインフラ整備を担う業界であるためです。
さらに今後も、国土交通省が進める国土強靭化基本計画によって、老朽化が進んだ公共インフラの維持・整備の需要拡大が見込まれています。
将来性のある土木業界で働いてみよう
この記事では、土木業界で行われている工事の種類を解説を交えながら、土木業界の現状と将来性について紹介してきました。土木業界は、私たちが生活する上で、欠かすことができない公共インフラ整備に携わる仕事です。
やりがいと将来性のある土木業界に少しでも興味があれば、参考にしてみてください。
当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。
おすすめ求人

編集部
建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。
株式会社夢真 コーポレートサイト