市場規模や働き方、海外進出など、世界の建築事情を総まとめ!

グローバル化が当たり前になってきた昨今、建設業界で働いている人の中には、海外の建設業界の情勢に関して気になる人も多いのではないでしょうか。
海外にも日本の都心部に負けず劣らず、高層ビルが立ち並ぶ地域は多いです。
アメリカのニューヨークや中国の北京、イギリスのロンドンなど世界各国の大都市には、大きな建物がたくさん集まっています。
建物の大きさや数だけでなく、外観の違いなどにプロならではの視点で着目している人もいるかもしれません。
海外の建物は日本の建物と建築様式が異なるため、外観も異なります。
現場監督なら、海外の建物と日本の建物の違いを知っておきたいところです。
また海外の大きな建物を見ていると、その国の建設業界の市場規模などについても知りたくなる人もいるかと思います。
世界には日本よりも建設業界の市場規模が大きい国もあります。
では、世界の建築事情について詳しく見ていきましょう。
この記事をお読みの方におすすめの求人
株式会社夢真が運営する求人サイト「施工管理求人サーチ」の中から、この記事をお読みの方にぴったりの「最新の求人」をご紹介します。当サイトは転職者の9割が年収UPに成功!ぜひご覧ください。
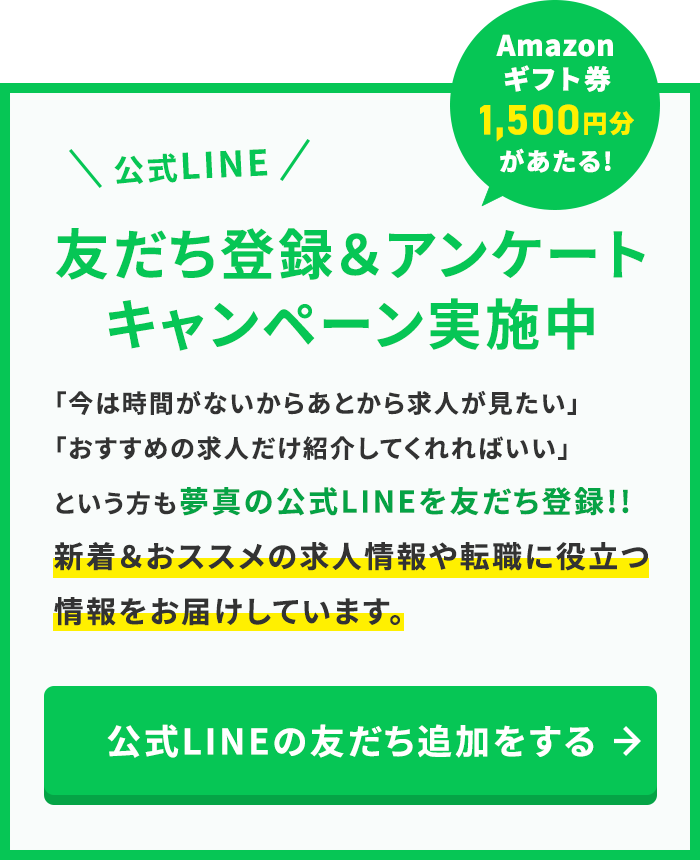
目次
世界の建設業界の市場規模ランキング!
1位中国
最近は、中国の経済成長が目覚ましいですが、建設業界の市場規模に関しても中国は現在1位です。
2015年時点で7,474ドルという水準で2位のアメリカをわずかに上回っています。
中国は人口が世界一多く、国土面積も広大。そのため人口に比例して建物も多く必要になります。
経済が成長して豊かになれば、新しいビルを建設しようという動きも広まって行き、都市部を中心に次から次へと大きな建物が建設されているのです。
建設会社の売上高に関しても、2000年代後半から急伸し、中国企業が欧米諸国の建設会社を凌駕しています。
ただ、中国の人口は2012年をピークで現在は減少に転じています。
そのため、今後もこの傾向が続くとは限りません。
現在のところ、右肩上がりで市場規模が拡大していますが、今後は減少に転じる可能性もあるでしょう。
2位アメリカ
アメリカも中国と同様に非常に広い国土を持ちます。
人口は中国ほど多くはありませんが、2017年時点で約3.3億人と日本の約2倍の規模です。
1990年代後半から2010年代初頭までは、建設業界の市場規模はアメリカが1位でした。
現在では急激に市場規模を拡大してきた中国に追い抜かれて2位の状態ですが、その差はそれほど大きくありません。
再びアメリカが中国を追い越して1位の座に返り咲く可能性もあります。
3位日本
日本の建設業界の市場規模は、中国とアメリカに次いで大きな水準です。
しかし、その差はかなり大きくアメリカの建設業界の市場規模が7321億円なのに対して日本は2576億円です。
実は1980年代後半から1990年代後半までの間は、日本が世界一の水準でした。
1990年代後半にアメリカに追い抜かれ、2000年代後半には中国に追い抜かれて現在に至ります。
4位はインド。5位以下は欧米諸国が並ぶ
4位はインドで、5位はイギリスです。
日本とアメリカの差も大きいですが、日本と4位のインドもやや大きな差があります。
イギリスとインドとの差は小さく、6位以下はドイツ、フランス、カナダと続きますが、いずれも大きな差はありません。
日本と海外の働き方の違いを比較
海外では、建設業界で仕事をする人たちの働き方も日本と異なります。では、どのような特徴があるのか主な国について見ていきましょう。
アメリカと日本
日本では、大きな工事はゼネコンが元請けになることが多いです。
ゼネコンでは実際の建設作業を行う職人を雇わず、下請けに仕事を割り振る役割を果たしています。
設計に関しては設計を専門に行う業者に依頼し、施工に関しては施工が専門の業者に依頼するという具合です。
しかし、アメリカには日本のようにゼネコンが設計と施工をそれぞれの専門業者に依頼するという構図はありません。
アメリカでは発注者が発注する時点で、設計と施工を分けています。
そもそも、アメリカでは日本のスーパーゼネコンのような企業は存在しません。
設計も施工もまとめて請け負う企業は存在しますが、規模は小さめです。
スーパーゼネコンが大きな力を持っている日本の建設業界とは根本的に異なるのです。
そして、建設業界で働く労働者の待遇や労働環境も、アメリカでは日本とかなり違いがあります。
日本では現在働き方改革の影響もあり、少しずつ改善してきていますが、建設業界で休日はあまり多くありません。
現状では、週休二日制を実現する途中の段階です。
これに対してアメリカでは、建設業も他の業種と比べて特段休日が少ないわけではありません。
これは主に、労働組合と労働生産性が大きく関係しています。
アメリカでは建設業界で働く労働者は、職種別の労働組合を組織して所属しているのが日本との大きな違いです。
そのため労働時間などの条件が厳格に守られており、長時間残業や休日出勤などをすることはほとんどありません。
また労働生産性も日本と比べるとかなり高く、同じ仕事をするのにアメリカだと日本よりも少ない人数と時間で行えます。
建設業界の職場環境の改善を図るにあたって、アメリカの建設業界は大いに参考になるでしょう。
中国と日本
中国の建設業界で働く労働者の待遇や労働環境は、日本と比べて良いものとは言えません。
中国の建設業界では、労働者の大半が十分な職業技能訓練を受けずに現場で仕事をしています。
そのため正しくない方法で作業をしてしまうケースも多く、建物の安全性に関わるようなこともあるかもしれません。
また、安全面での知識が乏しいことから、働いている労働者自身も仕事中に危険に晒される可能性があります。
こうした状況の背景には、中国で2000年代後半から建設需要が大きく増えたことが関係しています。
大きな建物が建設されているのは主に都市部ですが、農村部から多くの出稼ぎ労働者が都市部に出てくるようになりました。
人手が足りないため、知識や経験が乏しい人もどんどん作業に就かせているのです。
実は、日本でも一昔前までは似たような環境でしたが、少しずつ労働環境を改善して現在に至っています。
中国の建設業界も、あと10年から20年程度経てばもっと改善するかもしれません。
世界各国の建築様式の違い

国によって主流となる建築様式が異なります。
そのため、建物や街並みを見たときの印象も違ってくるでしょう。
ではイギリスや韓国、中国の建築様式について説明していきます。
近代のイギリス建築
イギリスでは、時代によって主流となる建築様式が移り変わってきました。
9世紀から12世紀あたりの時代に流行したのは、ロマネクス建築です。
ロンドン塔やダラムの大聖堂などが有名です。
12世紀後半から16世紀あたりまでの時代には、ゴシック建築が栄えました。
ステンドグラスを使っている建物や、先が尖ったデザインの教会やお城が多いのが特徴です。
15世紀後半から17世紀の初めにかけてはチューダー、エリザベス朝建築が流行しました。
ゴシック建築と似ていますが、安価なステンドグラスを使うことで、一般の住宅でも使われていた建築様式です。
17世紀から18世紀頃に流行したのはバロック様式です。
ルネサンスの影響を受けており、豪華な外観の建物がたくさん作られました。
18世紀前半にはジョージアン様式が流行しました。
エキゾチックな装飾や、建物全体の対称性にこだわるデザインが特徴です。
18世紀後半から19世紀にかけての時代には、ゴシック・リヴァイヴァル建築が流行しました。
ゴシック様式の復興運動から生まれたものです。
ウェストミンスター宮殿や学びの聖堂などが挙げられます。
20世紀初頭まではヴィクトリアン建築が流行しました。
石やレンガ、鉄、コンクリートなどを使い、ゴシック様式の流れをくんでいます。
韓国の伝統的な建築
韓国には、伝統的な「韓屋」と呼ばれる瓦屋根が特徴の建築様式があります。
韓国は地理的に日本に近いことから、気候も日本に似ていて、四季がはっきりしています。
夏には暑く冬には寒いため、韓屋は夏にできるだけ涼しく、冬にはできるだけ温かく過ごせるような工夫が凝らされているのです。
夏の暑さ対策として、地面と床との間に空間を作り、湿気を遮断して涼しく感じられるような構造の「板の間」があります。
冬の寒さ対策としては、床下にトンネルを作り、そこに煙を通すことで室内を温めるオンドルという床暖房が大きな特徴です。
こうした韓屋の建築様式は、既に三国時代のあたりから取り入れられていました。
ただ、現在ではアパートなどの集合住宅が増えたことから、韓屋の住宅は以前よりも減っています。
中国の建築
中国の建設業界は、労働環境や安全性に関して懸念されることが多いですが、建物を完成させるのが非常に早いです。
中国の長沙市にはスカイシティという57階建てのビルがありますが、そのビルはわずか19日間の工事で完成させました。
ごく簡素な作りなのではないかと思ってしまう人もいるかもしれません。
しかし、空調設備などもしっかりしておりエコな作りです。
4重窓を採用しており冷暖房効率が良いことから、二酸化炭素排出量が同程度の規模のビルと比べて少ないそうです。
この他にも15階建てのアークホテルを6日間で完成させた例もあります。
その早さの秘密は、工場内でパーツを作っていることと、豊富な労働力です。
現場での作業は基本的に組み立てるだけであるため、短時間で済みます。
これに加えて労働力が豊富であることから、工場も現場も24時間稼働させられるために、工事期間の大幅な短縮が実現しました。
世界の超高層ビルが多い街とは
日本にも東京都内を中心に大きなビルがたくさんありますが、世界には東京以上に超高層ビルが多い街もあります。
実物を見ると、東京で大きなビルを見慣れている人でも驚いてしまうかもしれません。
次に、世界の中でも超高層ビルが多い街を紹介していきます。
ヨーロッパ
ヨーロッパに対して超高層ビルが多そうなイメージを抱いている人もいるかもしれません。
しかし実は、意外と少なめです。
歴史的建造物が多いことから、景観を守るために規制がたくさんあり、あまり超高層ビルを建てられないのです。
それでも300メートルを超える巨大ビルが2つ存在します。
1つはイギリスのロンドンにある「シャード」というビルです。
2012年に完成したビルで、高さは310メートルあります。
東京タワーとほぼ同じ高さのビルです。
もう1つはロシアのモスクワにあるモスクワタワーで、302メートルの高さを誇ります。
モスクワには「ナーベレジナア」や「トライアンフ・パレス」、「サンクトペテルブルク・タワー」などもあります。
いずれも250メートルを超える超高層ビルです。
他にヨーロッパだとドイツのフランクフルトやフランスのパリに、200メートルを超える超高層ビルがいくつか集まっています。
アメリカ
アメリカでは、ニューヨークに超高層ビルが多く集まっています。
ニューヨークと聞いて超高層ビル群をイメージする人も多いでしょう。
その中でももっとも高いビルは「1_ワールドトレードセンタービル」です。
541メートルという高さを誇るビルですが、フィートに換算すると1,776フィートになり、これはアメリカ独立の年を表しています。
他にも「パークアベニュー」や「エンパイア・ステート・ビルディング」など非常に高いビルがニューヨークにはあります。
ニューヨーク以外だとシカゴも超高層ビルが多い街です。
「ウィリス・タワー」や「トランプ・インターナショナル・ホテル・アンド・タワー」など400メートルを超えるビルがあります。
中国
中国では上海に超高層ビルが多いです。
2016年に完成した「上海タワー」は632メートルの高さを誇り、世界で2番目に高いとされています。
他にも100メートルから200メートルくらいの高さのビルが非常に多く集まっており、ニューヨークと並んで超高層ビルの多い街と言えます。
日本企業の海外進出の状況とは
企業が市場を開拓するには、国内だけでなく海外にも目を向けなければなりません。
製造業などでは海外に製品を輸出している企業が多いですが、建設業においても海外進出をする動きが見られます。
東京オリンピック後は国内需要が減る可能性あり
現在、日本国内では建設需要が非常に多いです。
東京オリンピックに向けて新規でスポーツ施設を建設して、既存のスポーツ施設を改修するなどを行なっています。
スポーツ施設の他にもホテルなどの宿泊施設を作ったり、周辺の道路なども工事現場を見たりした人も多いのではないでしょうか。
建設需要がありすぎて人手不足が強く叫ばれている状態です。
しかし、東京オリンピックが終わった後はどうなるのか、はっきりとした見通しが立っていません。
東京オリンピック後も建設需要が見込まれるという見方もあれば、市場が冷え込むのではないかと懸念する見方もあります。
そのため、もし建設需要が減ってしまっても利益を確保できるように、大手ゼネコンを中心に海外市場を開拓しようと検討する建設会社が多いです。
国内需要だけでは供給が余ってしまうのであれば、海外に目を向けるのはごく自然な動きでしょう。
大手ゼネコンは既に海外拠点を設置している
海外市場を開拓すればいいということが分かっていても、そう簡単にできることではありません。
海外に拠点を設けるには多額の費用がかかり、海外で活躍できる人材も必要です。
そのため中小規模の建設会社にとっては難しいかもしれません。
大手ゼネコンに関しては、既に海外拠点を設置しているところも多いです。
特に東南アジアの地域に拠点を設置しているゼネコンが多く、東京オリンピック後は海外進出が本格化する可能性が高いでしょう。
アメリカやヨーロッパなどにも拠点を設置しているゼネコンもあります。

ゼネコンの求人、たくさんあります
業界最大級の求人数の中から、
年収にも働きやすさにもこだわった
「ゼネコン」の求人をどうぞ。
※転職成功率を上げたい人、コンサルタントに最適な求人を紹介してほしい人は2件以上の応募がおすすめです!
海外特有のリスクがネックになる
海外にどんどん拠点を増やしていけば、メリットと同時にリスクも発生します。その代表例が「為替リスク」です。
現地の通貨建てで取り引きをしている場合には、為替相場の変動により損失を被ってしまう可能性があります。
また海外の多くの地域は、日本ほど治安や政治が安定していません。
大きな政局の変化などにより、工事が途中で中断されてしまう可能性もあります。場合によっては工事代金を回収できなくなってしまうかもしれません。
また、治安が急激に悪化するなどの危険な状態になれば、工事の途中でも帰国せざるをえないでしょう。
他に法律や税制の違いなどにより、日本と同じように工事を行えないことも多いです。
建設業界の商慣習も国や地域によって異なります。
こうした違いに対する認識が甘いと、トラブルに遭遇してしまうかもしれません。
海外進出の際には、現地のことに関する詳細なリサーチが必要不可欠です。
建機業界も海外需要増
海外進出するにあたって、海外ではどの程度の建設需要が見込まれるのか把握しておく必要があります。
また、海外需要に対応するための人材も重要になってきます。
アジア地域で建設需要が見込まれる
最近では、アジア諸国の経済発展が目覚ましいです。
アジア諸国で本格的にインフラ設備を行うことになれば、それだけ建設需要も高まるでしょう。
国土交通省の資料によると、2030年までにアジアでの建設需要は年間1.5兆円以上にも上るそうです。気候変動などの影響も含めれば、もっと増えるかもしれません
また中国においては、建設業の市場規模が世界一の水準です。
日本のゼネコンにとってアジア地域の需要を狙わない手はないでしょう。
日本では、戦後長らく製造業において輸出を中心に稼いできましたが、これからは建設業においても海外で稼ぐ構図になりつつあります。
出典:厚生労働省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/common/001187356.pdf)
海外で働きたい人にとって大きなチャンス
建設業界で働いている人の中には、海外で活躍したいと思っている人もいるでしょう。
海外需要が多く、海外進出もどんどん推し進められている中で、自分も海外で仕事ができるのではないかと期待を寄せている人も多いです。
これまでなら、海外に赴任する現場監督は主にベテランの人だけでした。
しかし、海外進出が盛んになる中で、若手でも海外赴任になる人が増加傾向にあります。
入社1年目から海外で勤務するという人もいるくらいです。
海外勤務を希望する人にとっては嬉しい状況でしょう。
現場監督を現地採用することも
ゼネコンが海外で仕事をする際に、国内の社員が現場監督として現地に赴任するという方法が一般的でしょう。
しかし、現場監督の仕事を務められる人材が現地にいれば、現地の人材を使っても問題ありません。
そのため現場監督を現地採用する場合もあります。
ただ、現地で採用してそのまま現地で働くというのではなく、いったん日本に来てもらって研修などを実施しています。
現地の人材を育成して現地の仕事を任せるという方法です。
こうした方法も今後はどんどん増えていくでしょう。
海外出張も増える!?勤務のメリット

建設業界では、今後、海外出張が増えるとの見方が強まっています。
海外に拠点を置いている建設会社で働いている人なら、海外に転勤になることもあるかもしれません。海外勤務と聞くと不安に感じる人も多いですが、メリットもたくさんあります。
では、海外勤務をする場合のメリットと気をつけるべき点について見ていきましょう。
英語力を高めることができる
現在、現場監督の仕事をしている人の多くは、英語で外国人とコミュニケーションを取るのが難しいと考えているでしょう。
日本では、大半の人が中学校と高校で合計6年間英語を学び、大学でも英語を勉強する機会があります。
それにも関わらず、英語を話せる人というのはかなり少ないです。
大半の人は学生の頃にせっかく学んだ英語を活かせないでいます。
しかし、仕事で海外に行くことが決まればどうでしょうか。
英語を勉強し直すでしょう。
学生の頃にある程度学んでいることであるため、忘れていてもすぐに思い出せます。
そして、現地で仕事をしていく中で、話せる英語が見についていきます。
それが嬉しいと感じる人も多いです。
もし仕事で海外に行く機会がなければ、英語を使う機会にはほとんど出会えないでしょう。
英語以外の言語を身につけることができる
日本で暮らしていると英語以外の外国語に増える機会はほとんどありません。
しかし東南アジアでは、英語以外の言語を公用語とする国も多数あります。
もちろん英語が通じる国もありますが、必然的に現地の公用語を耳にする機会も出てくるでしょう。
日常会話程度なら、現地の公用語を使いこなせるようになることも多いです。
海外での勤務経験が今後のキャリア形成に役立つ
これまで日本国内だけで仕事をしてきた人にとって、海外勤務は何かと不安がつきまとうものです。
現地の現場の責任者として赴任するケースもあるため、職責も大きいでしょう。
しかし海外勤務においては、国内勤務だけでは得られないことも多く、海外ならではの経験もできます。
同僚も部下も職人さんも、ほとんどが外国人という中で仕事をすることになるでしょう。
そのような中で、無事に建物を完成させられたときの嬉しさは何物にも代えがたいです。
そして、自身の実績として会社に評価してもらえれば、今後のキャリア形成に大いに役立ちます。
海外の生活について知ることができる
海外での生活は、当然のことながら日本での生活とは異なる面があります。
文化や慣習も違えば、食べ物なども違うため、新たな発見が多いです。
仕事で長期滞在すると、海外旅行などで2、3日滞在しただけでは分からないことも発見できます。
見るもの聞くもの初めてのことばかりという状況で、ワクワクした気分になる人もいるでしょう。
刺激を求めている人にとっては充実した毎日を過ごせます。
海外で仕事をしたい現場監督へのアドバイス
海外で仕事をするにあたって、どんなことに気をつければいいのか、どんな準備をしておけばいいのか説明していきます。
最低限の英語や現地の言語を学習しておこう
海外で仕事をする上で必要になる英語力は、仕事の内容や環境によって差があります。
難しい商談などを行うのであれば、ビジネス会話を含めた高い英語力が求められるでしょう。
しかし、現場で職人さんに指示を出して、同僚や部下と仕事上の話をするくらいであれば、ハイレベルの英語力がなくても問題ありません。
ただ、それでも現地に出向く前に最低限の英語力は身につけておきましょう。
特に聞いたり話したりする能力が大事で、そのなかでも発音に注意しましょう。
英語は発音の仕方が良くないと、違った意味に受け取られてしまう場合もあります。
中学レベルの英語でも、正しい発音で聞いたり話したりできれば日常会話をこなすのに、さほど困ることはありません。
ビジネス会話などが必要な場合でも、現地で生活していく上で少しずつ覚えていけます。
現地の社会情勢や文化についてリサーチしておこう
海外で仕事をする上で、現地の社会情勢や文化などについて知っておくことはかなり大事です。
どんな国なのか、その地域独自の文化はどのようなものなのか、詳しくリサーチしておきましょう。
特に宗教に関することは、しっかり頭に入れておかなければなりません。
宗教により食べてはいけないものや、やってはいけないことなどがあります。
日本人の場合には、ほとんどの人が宗教に関して無頓着であるため注意が必要です。
宗教に関することを軽視していると、思わぬトラブルに発展してしまう可能性もあります。
トラブル防止のための対策を講じておこう
海外で仕事をする際にはトラブルに注意しなければなりません。
特に手続きに関してはミスがないようにしておきましょう。
国によってはパスポートだけでなく、就労許可を得なければならない場合もあります。
また犯罪に関しても十分な注意が必要です。
日本と同じ感覚でいると、スリや詐欺などの被害に遭ってしまうこともあります。
知らない人に対しては、決して気を許さないようにしましょう。
万が一何かあったときのために、日本大使館や総領事館の場所も確認しておくことをおすすめします。
海外勤務を希望する場合には
会社から海外勤務を命じられてから、英会話を勉強するなど慌てて準備をする人がいる一方で、自ら海外勤務を望んでいる人もいると思います。
しかし海外勤務を希望しているにも関わらず、なかなか海外に転勤にならないという人も少なくありません。
ここでは、海外勤務を希望している場合に何をすべきなのかを解説していきます。
上司に希望を伝える
建設業では今後、海外出張が増える可能性が高いですが、それでも国内で仕事をする人が圧倒的多数です。
海外に転勤になるのはほんの一部の人たちでしょう。
海外で働きたいのであれば、その一部の中に入らなければならず、かなり競争率が高いと言えます。
しかし、海外に転勤になる人の全てが海外勤務を望んでいるわけではありません。
国内だけで仕事をしたいと考えている人も多いです。
そのため海外勤務を希望するのであれば、そのことを上司に伝えておきましょう。
海外勤務を希望している人がいるというのであれば、人事の人たちもそれを尊重する形で検討してくれるかもしれません。
人事異動希望はなかなか通らないとよく言われるため、正式な希望は出さずに海外で働きたいことを上司に相談するのもいいでしょう。
数年後に希望が叶うこともあるかもしれません。
海外勤務は敬遠する人も多いため、やる気や熱意をアピールすることにも繋がります。
海外勤務がある建設会社に転職を検討する
スーパーゼネコンや準大手ゼネコンであれば、既に海外に拠点を設けているところも多いです。
以前から海外の仕事を請け負っているところもあります。
しかし、地方の地場ゼネコンや中小規模の建設会社では、まだ海外に拠点を設けていないところも多いです。
現在のところ海外の仕事を請け負う予定がない建設会社もあるでしょう。
地方で行われる工事を中心に請け負っている建設会社だと、海外進出にあまり積極的でないところもあります。
勤務先で海外の仕事を請け負わないことには、上司に相談してやる気をアピールしても海外勤務を実現するのは難しいです。
今後のキャリアアップなどを考えて、海外勤務を希望する意志が強いのであれば海外進出に積極的な建設会社への転職を検討してみましょう。
中には入社1年目から海外勤務になったという例もあります。
通常、海外勤務は、国内である程度の経験を積んだ人が命じられるケースが多いです。
しかし、海外進出が盛んな建設会社では、早い段階で海外経験を積ませるために、あえて若手のうちから海外の拠点に転勤させています。
ただ、会社の規模が大きければ海外進出に積極的とは限りません。
海外勤務を希望して転職したいのであれば、応募前に海外進出にどの程度積極的な企業なのかよく調べておくといいでしょう。
国内で現場監督としての十分なキャリアを積む
社員に若手のうちから海外経験を積ませようという方針の企業なら、現場監督としての経験が浅い状態で海外勤務を命じられることも多いです。
その場合には、現場監督として必要な基本的な経験も海外で積むことになります。
しかし多くの場合、国内で現場監督としての役割を十分に果たせる経験と能力のある人でないと海外勤務は厳しいです。
若手で海外勤務になるのは例外的なケースと考えていいでしょう。
そのため、海外の現場で現場監督として活躍したいのであれば、まずは国内で現場監督として十分なキャリアを積まなければなりません。
国内の現場で現場監督としての仕事がまだ十分にできていないと、海外で活躍するのは難しいでしょう。
英会話の勉強をしておく
海外勤務になることが分かってから英会話の勉強を始める人は多いです。
英語そのものは中学や高校で学習しているため、短期間で集中して勉強すれば、ある程度は英会話を話せるようになります。
しかし、自ら海外勤務を希望している場合には、いつ海外勤務を命じられても大丈夫なように、普段から英会話を勉強しておくといいでしょう。
現場監督の仕事は忙しいため、なかなか時間が取れないかもしれませんが、最近ではオンラインで英会話を学習できるサービスもあります。
そのため、少し空いた時間を上手に利用して英会話を学ぶことも可能です。
また、海外進出に積極的な建設会社への転職を検討しているのであれば、英語の資格を取得するのも有用です。資格を取ることで、自分の英語力を客観的に把握することもでき、海外勤務を希望する意志が強いということも伝わるでしょう。
これからの建設業は海外に目を向けなければならない
一昔前までは建設業で働く人にとって海外のことはあまり気にしなくて済んでいました。
しかし最近では、主にアジアの地域で建設需要が増えていることから、大手ゼネコンを中心に海外進出が盛んです。
今後は、現場監督としてのキャリアを積む上で海外勤務も経験するかもしれません。
海外では建物の主な建築様式や工事の方法なども異なります。
そのような海外の現場での仕事を経験すると、日本に帰国してからも活かせることがたくさんあるでしょう
関連記事:
【グローバルな視点で確認】アメリカと日本の建設業界の働き方の違い。
この記事をお読みの方におすすめの求人
株式会社夢真が運営する求人サイト「施工管理求人サーチ」の中から、この記事をお読みの方にぴったりの「最新の求人」をご紹介します。当サイトは転職者の9割が年収UPに成功!ぜひご覧ください。

当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。
おすすめ求人

編集部
建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。
株式会社夢真 コーポレートサイト

































