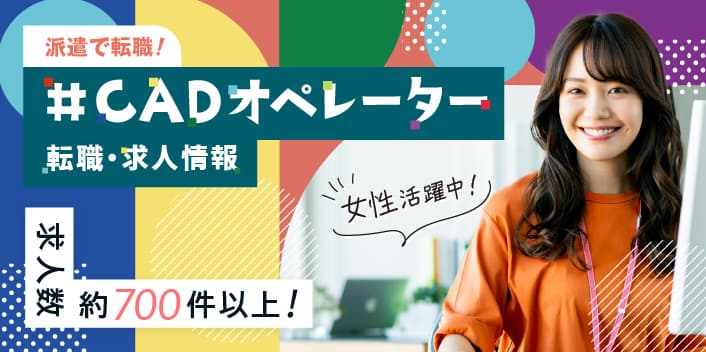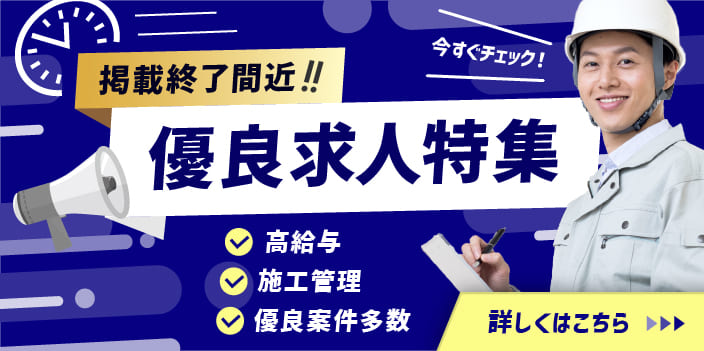マスカーブ(土積曲線)図表を見るポイント5つ|出題されやすい資格とは?
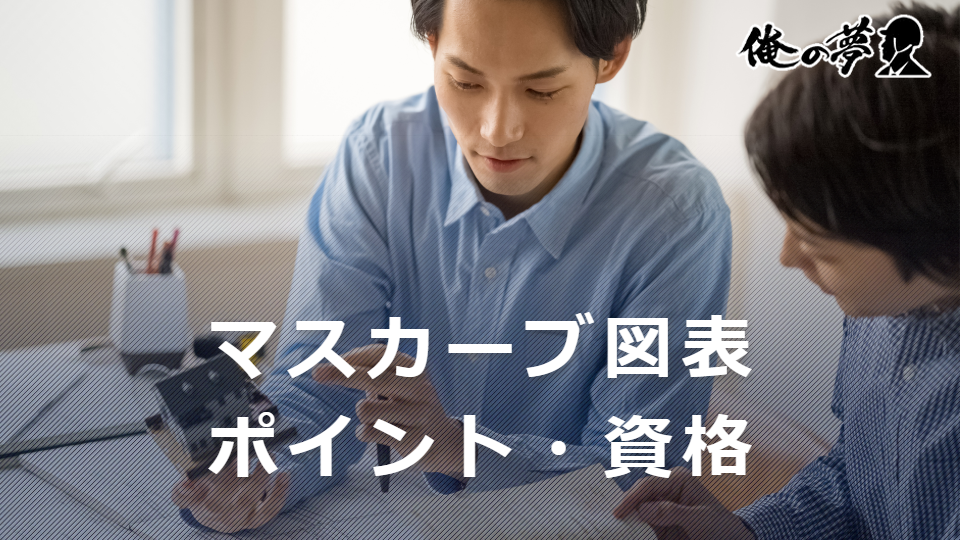
目次
マスカーブ(土積曲線)とは
マスカーブ(土積曲線)とは、土量の累計量を示している曲線のことです。
マスカーブの上がり勾配部分は切土部分(地面を削りとって、地盤面を低くした部分)を、下り勾配は盛土部分(土を盛って地盤面を高くした部分)を表しています。
このマスカーブは、切土と盛土のバランスを測り、土工事において土の運搬計画を立てる際に用いられます。
運土形態ごとの土量計算法
土工事において、土量の配分計画は工期と工事費に大きな影響を与えます。そのため、無計画に土を運搬しないよう、施工対象となる区域で土量計算を行い、土量配分計画を立てる必要があります。
土量計算を行う方法は運土形態によって異なります。土工事には線土工と面土工の2種類があり、それぞれの形態に適した土量計算法を用います。
線土工は平均断面法
道路や鉄道、堤防工事のような線状の運土工を線土工と呼びます。線土工では平均断面法を用いて土量計算を行います。
平均断面法は、両端の断面積の平均と両端断面区間の距離を乗じて、両端断面区間の体積を求める方法です。線状の土量を把握しやすいのが特徴です。
面土工はメッシュ法(柱状法)
面土工は、宅地造成や敷地造成など面的な広がりを持つ運土工のことです。面土工では、メッシュ法(柱状法)を用いて土量計算します。
メッシュ法とは、埋立地の平面図に一定の間隔で格子を引き、各格子の中央点または交点の現状標高と埋立後の標高の差から埋立の高さを求め、各格子の水平面積に乗じることで各格子の容量を求める方法です。メッシュ法は面状土量の把握に適しています。
マスカーブ(土積曲線)図表を見るポイント5つ
次に、マスカーブ(土量曲線)図表を正しく読み取るためのポイントをご紹介します。
マスカーブは土量の累計を表しており、道路工事などで土量配分計画を作成する際に用いられるものです。縦軸と横軸の意味、グラフの形が表す意味、ゼロが表す意味などを理解しておきましょう。
1:縦軸と横軸の意味
まずは、マスカーブの縦軸と横軸の意味を知りましょう。
マスカーブの縦軸は始点からの土工量の和を、横軸は始点からの距離(測点位置)を表しています。測点とは、工事の起点をゼロとした時、工事終点にむけた中心線上に一定の間隔で設置する管理ポイントのことです。
グラフの曲線が上下変化は、測点位置区間での土の増減を表しています。
測点位置で縦軸がプラスになっていたら土が余っている状態です。その場合は、余った土を近くの不足箇所へと運びます。逆に縦軸がマイナスの地点は土が足りない状態なので、近くの余剰土を運んで来る必要があります。
2:開始は土の増減がないので土量ゼロ
グラフの左端、マスカーブの開始地点は工事のスタート地点に当たります。工事の開始地点なので土の増減はまだなく、グラフ縦軸である土量はゼロになります。
工事が始まり切土や盛土を行うことで、土量の増減が起こりグラフ曲線もそれに伴って変化していきます。
3:右上がりは土が発生
マスカーブが右上がりになっている所は、その区間で切土を行い土が発生していることを表しています。
切土は地面を低くするために地面を削っていく作業です。そのため、大量の土が発生します。その結果、切土区間ではマスカーブの曲線は土量が増えることを表す右上がりの形になります。
4:右下がりは土が減少
逆に、グラフが右下がりになっている所は盛土を行い土が減少していることを表しています。
盛土は地盤面を高くするために土を盛っていく作業です。埋立には大量の土を使います。そのため、盛土区間ではマスカーブの曲線は土の量が減っていることを表す右下がりの形になります。
5:最終測点の数値に注目
最終的に土が不足しているのか余っているのかは、最終測点の数値を見ることで分かります。
最終の測点でプラスになっていれば土が余っている状態、マイナスであれば土が不足している状態だと言えます。ゼロになっている場合は、切土量と盛土量が均衡している状態を表しています。
マスカーブ(土積曲線)が出題されやすい資格
マスカーブ(土積曲線)は、土木施工管理技術検定において出題されることがあります。土木施行管理技術検定は土木施行管理技士の資格を取るための試験で、土木工事においてとても重要な資格です。
マスカーブは、この検定において数年に一度出題される傾向にあります。
一級土木施工管理技術
土木施工管理技術検定制度は、建設業法第27条に基づき国土交通大臣指定の機関が実施する国家試験です。所定の実務経験を持つ者が検定に合格し所定の手続きを取ると技術検定合格者となり、土木施工管理技士の称号を与えられます。
1級土木施工管理技士の資格を取得すると、該当する工事での監理技術者、または主任技術者になることができます。
7種の指定建設業にかかわる特定建設業者は特定の工事において監理技術者や主任技術者を置く必要があり、それには1級施工管理技士等の国家資格を持った者が必要です。そのため、土木施工管理技士の資格は建設業界においてとても重要な資格と言えます。
この1級土木施行管理技術検定の試験で、マスカーブに関する問題が出題されることがあります。
出典:1級土木施工管理技術検定 | 一般財団法人全国建設研修センター
参照:https://www.jctc.jp/exam/doboku-1
二級土木施工実地試験
二級土木施工管理技術検定は、2級土木施工管理技士の資格を得るための試験です。1級と同様、国土交通大臣指定の機関が実施する国家試験です。
2級土木施工管理技士の資格を取得すると、特定の工事において、作業工程ごとの責任者である主任技術者になることができます。
この二級土木施行管理技術検定の試験でも、マスカーブに関する問題が出題されることがあります。
マスカーブ(土積曲線)の見方を覚えよう
マスカーブ(土積曲線)とは、土木工事における土量の累計量を示す曲線のことです。
マスカーブの縦軸は土量を、横軸は測点地点を表しており、グラフが右上がりの区間は切土部分で土の量が増えている、右下がりの区間は盛土部分で土の量が減っていることを表します。
マスカーブは、土木工事において土の運搬計画を立てる時に用います。土木工事において土の運搬は工期や工事費に大きく影響を与えるため、マスカーブを用いてできるだけ合理的に土を配分する必要があります。
マスカーブは土木施工管理技士の試験にも出題されます。マスカーブの見方を覚えて、正しく読み取りましょう。
当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。
おすすめ求人

編集部
建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。
株式会社夢真 コーポレートサイト