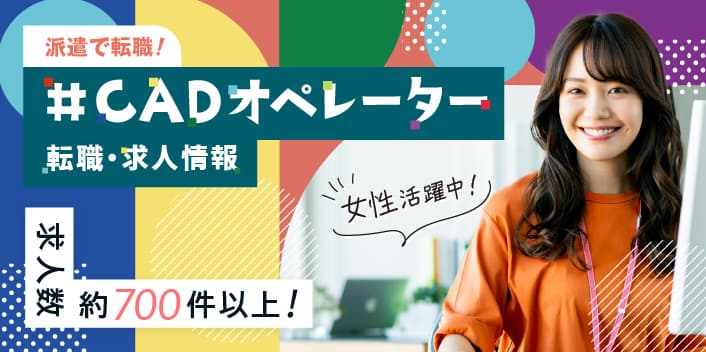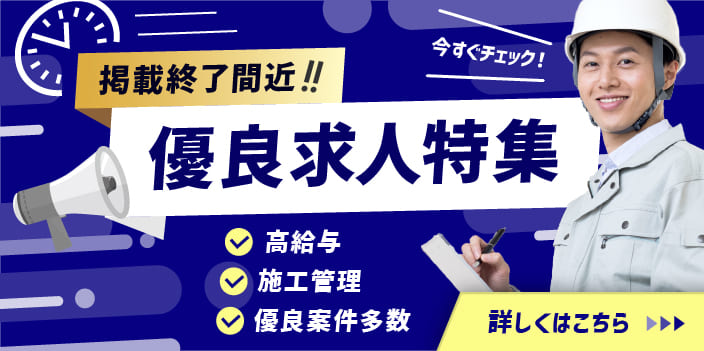スレーキング材料を使用する時の対策4つ|スレーキングの影響もわかりやすく紹介

最短30秒で予約!転職のプロに相談しよう
施工管理として今より良い条件で働きたい方は、夢真にお任せください!
目次
スレーキングとは
スレーキングとは、掘削時には硬い岩石だったものが細粒化し、崩壊する現象です。
スレーキングの発生メカニズムには2つの考え方があり、1つは乾燥と吸水の繰り返しによって収縮膨張現象が発生し、岩石に細かいひび割れが発生することによって物質が破壊されていくというものです。
もう1つは乾燥した状態でひび割れに水が浸み込み、隙間の空気が圧縮されて空気圧が上昇することで物質が破壊されるというものです。
スレーキン グ性材料とは
スレーキング性材料とはスレーキングが発生する軟岩や土塊などです。
乾燥と吸水が繰り返されることで細かく細粒化するスレーキング性材料は、新第三期時代に堆積した凝灰岩や泥岩などに多く存在します。
スレーキング性材料は掘削の段階では硬い塊の状態で産出されますが、盛土に利用すると施工後の雨と乾燥の影響でだんだんと細粒化します。そのため、スレーキング性材料は盛土を沈下させたり強度を低下させる原因になります。
主なスレーキング試験方法

スレーキングの試験方法にはいくつかの種類があります。
前述のとおり、スレーキング性材料を盛土などの施工に使用すると、施工してから沈下の被害が発生するケースがあります。完成してから8年後に約70cm沈下した事例があります。
このような被害をなくすためには、事前に岩石の強さを試験する必要があります。ここでは、主なスレーキング試験方法についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
浸水崩壊度試験
浸水崩壊度試験とは、岩石の形状変化を調べる試験です。
岩石を80℃で24時間乾燥させたのち、水浸させて、水浸直後から30分、1時間、2時間、4時間、6時間、さらに24時間経過ごとに目視によって観察し、その崩壊度をAからDの4段階で評価します。
試験日数は1週間から10日間ほどで、試験に必要な岩石量は5cmから8cmほどの岩塊もしくはコアとなります。
岩の乾湿繰返し吸水率試験
岩の乾湿繰返し吸水率試験とは、切土法面の風化に対する耐久性を調べる試験です。
試験対象の岩石の質量を測定し、24時間水浸後に水のみを捨てて崩壊した土などを含めた吸水後の質量を測定し、次は110±5℃で乾燥させて乾燥後の質量を測定します。
この作業を10サイクル続け、1サイクルごとに含水比を求め、風化に対する耐久性を評価します。
スレーキング材料を使用する時の対策4つ
スレーキング材料を使用する場合には4つの対策があります。
ここまでご紹介したとおり、脆弱なスレーキング材料を盛土の施工に使用することで沈下などの被害が発生するケースがありますが、実際には建設残土削減のためにスレーキング材料であっても現場で使用する必要があります。
ここでは、スレーキング材料を使用する時の対策4つをご紹介しますので、どのような対策があるのかぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。
スレーキング材料の対策1:破砕転圧
スレーキング材料の対策の1つ目は、「破砕転圧」です。
破砕転圧とは転圧の際にあらかじめ破砕しておくことです。スレーキング材料は施工後に風化によって圧縮沈下するリスクがありますので、先に破砕しておくことが有効です。

ゼネコンの求人、たくさんあります
業界最大級の求人数の中から、
年収にも働きやすさにもこだわった
「ゼネコン」の求人をどうぞ。
※転職成功率を上げたい人、コンサルタントに最適な求人を紹介してほしい人は2件以上の応募がおすすめです!
また、破砕転圧を行う場合は掘削段階から十分に破砕できる掘削方法について検討し、タンピングローラーで破砕転圧を行う場合は、薄層で締め固めることによって沈下を低減できることなどに留意しておくようにしましょう。
スレーキング材料の対策2:安定処理
スレーキング材料の対策の2つ目は、「安定処理」です。
安定処理とは、石灰やセメントなどの改良剤を使用することで土壌を改良する方法です。
前述の破砕転圧に効果がない場合、安定処理を行うことで土壌改良する方法があります。また、安定処理を行う場合は事前にスレーキング材料を細かく破砕した状態で改良剤を混合し、さらに効果を確認した上で用いるようにしましょう。
スレーキング材料の対策3:排水処理
スレーキング材料の対策の3つ目は、「排水処理」です。
排水処理とは土壌の地表面排水や湧水処理、地下排水工などを行うことです。
スレーキングは乾燥と吸水が繰り返されることによって発生するため、地下水や浸透水などが大きな影響を与えています。そのため、スレーキング材料であることが分かっている場合は、排水処理を徹底することで影響を軽減させることができます。
スレーキング材料の対策4:品質管理
スレーキング材料の対策の4つ目は、品質管理です。
工法規定方式で品質管理することがスレーキング材料には有効です。
一般的に、空気間隙率が15%以下になることで圧縮力による物質のひずみは収束する性質があることがわかっています。
そのため、排水処理を行ったうえで破砕転圧や安定処理を行い、空気間隙率を15%以下に保てるようなモデル施工によって品質管理を行うことで、スレーキングを発生させないようにすることも可能になります。
スレーキングの影響
スレーキングによってさまざまな影響があります。
盛土にスレーキング性材料である脆弱な岩塊などを使用することで、施工後に多くの問題が発生する可能性があります。
ここでは最後に、スレーキングによってどのような影響があるのかご紹介しますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
安定性の低下
スレーキングによって盛土の安定性が大きく低下することがあります。
スレーキング材料は建設時には問題ない良好な盛土材料であっても、スレーキングによってだんだんと風化し、泥濘化することで、長期的な盛土としての安定性の低下が発生します。
また、盛土の下部にある泥岩がスレーキングしたことにより、安定性を失った盛土が崩れた事例もあります。
盛土の崩壊
スレーキングによって盛土自体が崩壊することがあります。
スレーキングによって盛土に使用された土塊や岩石などが崩壊することにより、盛土の強度を低下させます。
また、スレーキングの発生によって盛土の土粒子が細粒化していたことにより、地震発生時に盛土の法面崩壊などが発生した事例もあります。
スレーキングについて知ろう
スレーキング性材料は風化によって簡単に崩れるリスクがあります。
また、一見良質な岩石であるケースもありますので、事前にスレーキング試験によって岩石の強度を確かめる必要があります。
ぜひ、この記事でご紹介したスレーキングの概要や試験方法、スレーキング材料を使用する時の対策などを参考に、建設現場において十分注意しなければいけないスレーキングについて理解を深めてみてはいかがでしょうか。
当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。
おすすめ求人

編集部
建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。
株式会社夢真 コーポレートサイト