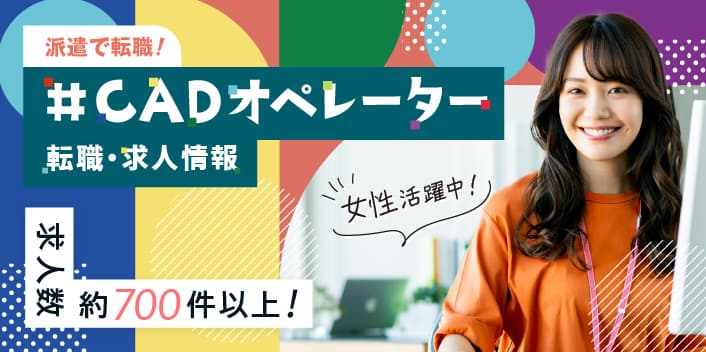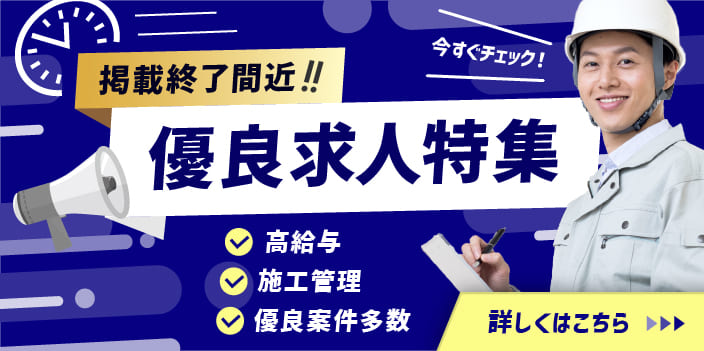洗堀被災が起きる原因5つ|洗堀を防ぐ水防工法もあわせてご紹介!

最短30秒で予約!転職のプロに相談しよう
施工管理として今より良い条件で働きたい方は、夢真にお任せください!
目次
洗堀とは
洗堀とは水の流れにより、河岸や河床などの土砂が洗い流される現象のことです。
洗掘によって橋梁が流されたり決壊したりすることがあります。そのため、河川などに構造物を設置する場合、洗掘によって構造物が流されたり固定している部分が緩まないように、さまざまな洗掘防止加工が行われます。
また、洗掘は主に水流によって構造物などが物理的に侵食されることを指します。
浸食との違い
浸食は水や風などの外的な力によって岩盤などが削られることを意味します。
「浸食」は岩石や地層が削られる原因が雨水や河川の流れなどの水の力に限定しているわけではないため、「侵食」という表記が一般的です。
一方、洗掘は波の影響や川の流れなど、水の力により物体が影響を受けることを指しているという違いがあります。
洗堀被災の原因5つ
洗堀被災にはさまざまな原因があります。
雨などにより河川が増水し、洗掘によって橋梁などに被害が発生することを「洗掘被災」、「洗掘被害」といった言葉で表します。日本では、大雨増水時には橋梁が流されるといった被害が発生することも多いです。
ここでは洗堀被災の原因5つをご紹介しますので、どのような原因で被災が発生するのか参考にしてみてください。
洗堀被災の原因1:河床洗堀
河床洗堀とは河床が水の流れなどの力によって削られていくことです。
言葉のとおり、河床が流水の作用で洗掘されていくことを意味します。河床は一般的に中流部には砂利、下流部には細かい砂などが蓄積しているため、水の流れによってだんだんと土砂が洗い流されていきます。
そのため、河床洗堀によって護岸の基礎部に空洞が発生し、土砂が空洞へ流出して護岸の沈下や陥没、倒壊などの被害が発生するケースがあります。
洗堀被災の原因2:吸い出し
吸い出しとは土砂が水の流れなどの力によって流れ出ていってしまうことです。
大雨などによる河川の増水時には、護岸裏法部の土砂が吸い出しによって流出し、護岸背面の土砂が陥没して護岸全体が被災するケースがあります。
吸い出し防止には、石やブロックなどを積み上げるといった方法で対策を取ります。
洗堀被災の原因3:流体力
流体力とは空気や水の力によって引き起こされる力を指す言葉です。
岸壁や防波堤、ダムなどの水理構造物には流体力が作用します。そのため、建築業界において構造物周辺の水の流れや構造物に作用する流体力について把握することは非常に重要です。
たとえば、洪水時には河岸のブロックにさまざまな力がかかることで、ブロックが流出することがあります。さらに1つのブロックが流出することで流体力が増大し、流出範囲も拡大します。
洗堀被災の原因4:残留水圧
残留水圧は洪水減水の際に浸透水が取り残されることにより発生します。
堤体内や河岸の地中に浸透水が残っていると残留圧力が発生し、パイピングを発生させることがあります。パイピングとは滞水がある流路から土砂と水が噴き出すことです。
また、護岸の勾配が急な場合は土圧に残留圧力が加わることにより護岸が転倒したり、地質強度が低下することで滑り被災を発生させることがあります。

ゼネコンの求人、たくさんあります
業界最大級の求人数の中から、
年収にも働きやすさにもこだわった
「ゼネコン」の求人をどうぞ。
※転職成功率を上げたい人、コンサルタントに最適な求人を紹介してほしい人は2件以上の応募がおすすめです!
洗堀被災の原因5:天端の侵食
護岸天端から浸食されることで護岸裏が空洞化することがあります。
洪水が護岸の天端を超える場合や高水敷から水が落ち込んで流れが激しくなっている場合では、天端からの浸食によって護岸裏が空洞化して被災に至るケースがあります。
外岸側に寄せられた水の流れは遠心力と釣り合うように水位を上昇させますが、水位が護岸に乗り上げると速い流れや天端から水路へ落ちる流れが発生するため、土砂を大きく侵食することになります。
洗堀を防ぐ水防工法4選

洗堀を防ぐ水防工法にはどのような種類があるのでしょうか。
ここまでご紹介したとおり、水の流れを主な原因とする洗掘によって、護岸や橋梁が大きな被害を受けることがあります。そのため、河川などに構造物を設置する場合には洗掘を防止するための水防工法が取られており、被害の発生を防ぐことになります。
ここでは最後に洗堀を防ぐ水防工法4選をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
洗堀を防ぐ水防工法1:シート張り
シート張りとは堤防が洪水流などによって洗掘や漏水などの被害を受けた場合に使用する工法です。
シート張りは堤防などに決壊箇所が発生した場合に、水の流れから堤防の洗掘などの被害拡大を防止するために行われるものです。
具体的な方法としては、防水シートの上下や中間に竹などを取り付け、決壊している場所を覆うようにシートを下ろし、重石として土嚢を取りつけます。
洗堀を防ぐ水防工法2:木流し
木流しとは主に急流部での流水の緩和を目的として使用する工法です。
木流しで流水を緩和することにより堤防決壊の拡大防止や、緩流部での波欠けのために用いられます。
具体的な方法としては、まず竹や枝葉の茂っている樹木を根元から切り、枝に土嚢や石俵などを取り付けます。次に鉄線で縛った根本の一端を留杭に結束して、流しかけることで固定させます。
洗堀を防ぐ水防工法3:捨石
捨石とは適当なサイズの石を水中に沈める工法です。
捨石は主に水際の洗掘防止のために用いられる工法で、水流を弱めるために水中に投入される石のことを指します。
また、河床に基礎を作る際にも捨石が用いられるため、防波堤の基礎マウンドの建設工事を指して捨石と言うこともあります。
洗堀を防ぐ水防工法4:沈床
沈床とは玉石や割栗石を詰めた格子枠を河床に沈める工法です。
構造物の地盤が水流によって洗掘されることを防ぐために、河床の補強として用いられる木製もしくはコンクリート製の枠です。
日本では主に「粗朶沈床」と呼ばれる束ね粗朶で作った格子と敷き粗朶、詰め石を交互に重ねた沈床が使用されます。
洗堀について知ろう
河川などに構造物を設置する場合、洗掘による被災が発生する可能性を考える必要があります。
ぜひこの記事でご紹介した洗堀被災の原因や洗堀を防ぐ水防工法などを参考に、洗掘やその防止策について理解を深めてみてはいかがでしょうか。
当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。
おすすめ求人

編集部
建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。
株式会社夢真 コーポレートサイト