建築士が独立するには?年収や失敗しない方法・何年かかるか解説

「建築士として独立したら、年収はどれくらい上がる?」
「建築士で独立するのは難しい?独立までに何年かかる?」
建築士として独立を検討していれば、上記のような疑問や悩みが頭の中に浮かんでいるはずです。
せっかく独立するのなら、是が非でも成功を収めたいものですが、そのためには事前の知識と準備が欠かせません。
そこで当記事では、建築士として独立することのメリット・デメリット、向いている人・いない人から、年収や失敗しない方法、何年で独立できるかについてまで徹底解説していきます。
建築士として独立を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
この記事をお読みの方におすすめの求人
株式会社夢真が運営する求人サイト「施工管理求人サーチ」の中から、この記事をお読みの方にぴったりの「最新の求人」をご紹介します。当サイトは転職者の9割が年収UPに成功!ぜひご覧ください。
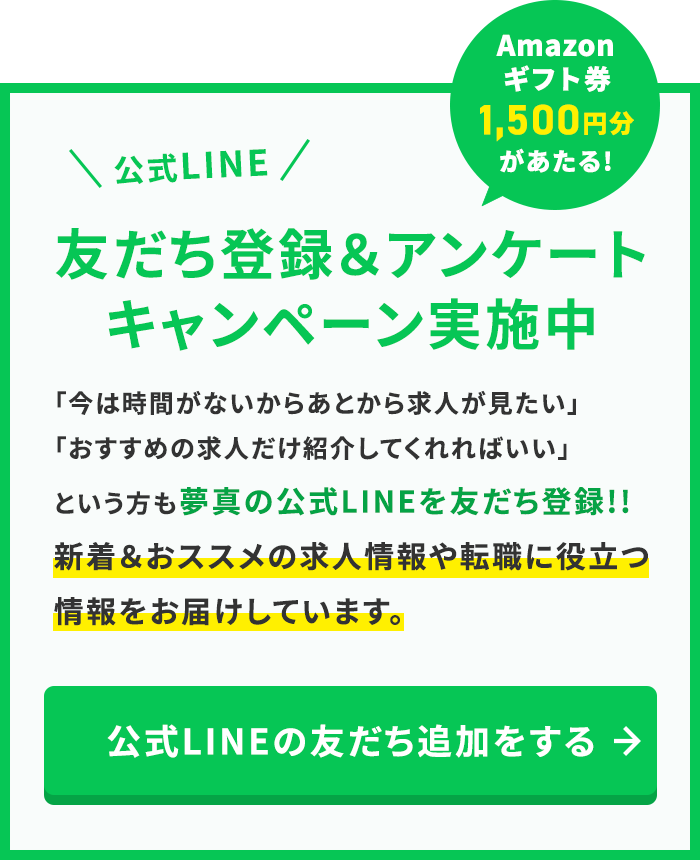
目次
建築士の仕事内容は?
建築士は建物の設計や工事監理ができる資格で、以下3種類に分類されます。
| 資格名 | 設計できる主な建物 |
|---|---|
| 一級建築士 | 高層ビルやマンション、学校や病院など大規模な建物 |
| 二級建築士 | 住宅など小規模な建物 |
| 木造建築士 | 木造の建物 |
資格によって設計できる建物の規模や種類が異なり、一級建築士になれば制限なく建物の設計や工事監理が可能です。
それぞれの詳しい仕事内容については以下の記事に詳しくまとめているので、ぜひ参考にしてください。
※関連記事:建築士の仕事内容をわかりやすく紹介|設計士との違いや建築士になる方法も解説
独立した一級建築士の年収は?
企業勤めの一級建築士の場合、平均年収は約720万円です。
「令和3年分 民間給与実態統計調査」によれば、給与所得者全体の平均年収は443万円なので、一級建築士の平均年収はそれより300万円ちかくも高いことになります。
一級建築士の年収や給料については以下の記事に詳しくまとめているので、こちらもぜひ参考にしてください。
※関連記事:一級建築士の平均年収・給料は?年齢別による違いや収入を上げる方法を紹介
企業勤めでも年収は高い傾向にある一級建築士ですが、独立に成功すれば、これ以上の金額を稼げます。
個人差が大きいため、明確にいくらとは言い難いものの、年収で1,000万円やそれ以上を稼ぐことも可能です。
建築士が独立するメリット
建築士が独立するメリットは、主に以下2つあります。
- 能力次第で会社員時代より高い年収が狙える
- 仕事の自由度が高くなる
それぞれのメリットについて、説明していきます。
能力次第で会社員時代より高い年収が狙える
1つ目のメリットは、スキル次第で会社員の建築士より高い年収が狙えることです。
会社員の場合、会社で決められた給与以上のお金を稼ぐのは困難です。
その点、独立すれば、仕事を受けた分だけ報酬が得られるうえ、人気の建築士ともなれば報酬額も高く設定できるため、得られる収入の額は跳ね上がります。
仕事の自由度が高くなる
仕事の自由度が高くなる点も、独立によって享受できるメリットです。
独立すれば、自分が経営者になるので、受ける案件や仕事をする時間を決められます。
会社での給料の額は会社が決めますが、仕事の報酬額を自分で決められることも独立の醍醐味の1つです。
建築士が独立するデメリット
建築士が独立することには、主に以下2つのデメリットもあります。
- 仕事が軌道に乗るまではかえって年収が下がるリスクがある
- 独立に失敗するリスクがある
それぞれのデメリットについて、説明していきます。
仕事が軌道に乗るまではかえって年収が下がるリスクがある
建築士として独立しても、仕事が軌道に乗るまではかえって年収が下がってしまう可能性があります。
特に独立初期は実績がないため、仕事を受注するのも一苦労です。
建築士の場合、もともとの年収が平均より高い傾向にあるため、他の業種以上に年収が下がる可能性は高いと言えるでしょう。
独立に失敗するリスクがある
建築士に限らず、独立には失敗のリスクも付きものです。
収入額が下がったり、不安定になったりするだけでなく、場合によっては大きな借金を背負ってしまうリスクもあるため、独立は入念な準備のもと、慎重に行わなければなりません。
建築士として独立するのに向いている人・向いていない人
建築士として独立するのには、向いている人と向いていない人がいます。
それぞれの特徴について、説明していきます。
向いている人の特徴
建築士として独立するのに向いている人は、以下の特徴を持つ人です。
- 専門的な知識と技術力がある人
- 創造性とデザイン能力がある人
- 独立心や自己管理能力がある人
建築士として独立して成功するには、建築設計や施工に関する知識と技術が必要で、法律や規制に関する知識も欠かせません。
建築設計は、クライアントの要望や予算に合わせて、美しく機能的な建物をデザインすることが求められます。
創造性やデザイン能力がある人は、独立して仕事をするうえで有利です。
独立して仕事をするには、独立心が必要です。
自己管理能力も重要で、スケジュールやタスク管理ができる人が向いています。
以上のような特徴やスキルを持っている人が、建築士として独立するのに向いていると言えます。
ただし、独立する前には、ビジネスや法律に関する知識を身につけることも重要です。
向いていない人の特徴
建築士として独立するのに向いていない人は、以下の特徴を持つ人です。
- 専門的な知識と技術力が不足している
- コミュニケーション能力が不足している
- 経営能力が不足している
建築士としての知識や技術力が不足した状態で独立してしまうと、失敗する確立は高いと言えます。
また、建築士は、クライアントや建設業者とのコミュニケーションが欠かせません。
相手の要望を理解し、自分のアイデアを伝えるためのコミュニケーション能力が足りなければ、継続的な仕事の受注には結びつきません。
独立して仕事をする場合、建築士としてのスキルだけでなく、ビジネスの面でも経営能力が求められます。
経営能力がなければ、長期的に安定して活動することは困難です。
「自分は独立には向いていない」または「まだ早い」と感じた方は、独立に必要な知識やスキルを身につけるために、もう数年間実務経験を積んだほうが賢明です。
効率良く必要な知識やスキルを身につけたいなら、転職をおすすめします。
当社・株式会社夢真が運営する施工管理求人「施工管理求人サーチ」では、全国に常時6,000件以上の求人を取り揃えています。
この豊富な求人の中から、あなたの希望条件にマッチしたものをご紹介するので、今の職場より知識やスキルを身につけられる仕事に出会えます。
また、施工管理求人サーチでは9割以上の方が年収アップに成功しているので、今の年収に不満があって、年収を上げるために独立したいという方もぜひ利用を検討してみてください。
建築士の独立で成功するのは難しい?失敗しないための準備方法
建築士が独立して成功するのは簡単なことではなく、数年単位での入念な準備が欠かせません。
独立失敗を防ぐうえで重要な準備方法は、以下のとおりです。
- 設計事務所などで実務経験を積む
- 建築士の資格を取得する
- 実務を通じて人脈を広げる
- 独立に向けて資金を貯めておく
- 関連資格を取得しておく
- 建築士事務所の登録を行う
それぞれの準備方法について、解説していきます。
設計事務所などで実務経験を積む
まずは建築士として働ける企業に勤めて、実務経験を積みましょう。
建築士として働ける企業には、主に以下のものがあります。
- 設計事務所
- ゼネコン
- ハウスメーカー
- 工務店
実務経験を積まなければ、独立はもちろん、独立に必要な資格も取得できません。
独立に備えて、まずはしっかり足場を固めましょう。
建築士の資格を取得する
建築士の資格には、以下の種類があります。

ゼネコンの求人、たくさんあります
業界最大級の求人数の中から、
年収にも働きやすさにもこだわった
「ゼネコン」の求人をどうぞ。
※転職成功率を上げたい人、コンサルタントに最適な求人を紹介してほしい人は2件以上の応募がおすすめです!
| 資格名 | 受験資格 |
|---|---|
| 一級建築士 | 二級建築士として実務経験4年以上 |
| 二級建築士 | 実務経験7年以上 |
| 木造建築士 | 実務経験7年以上 |
※受験資格は大学等の指定科目を修めていない場合のもの
建築に関する学歴がない場合、建築士の受験資格を満たすには、上記のようにいずれも長い実務経験が必要です。
加えて、難関とも言われる試験に合格しなければなりません。
令和4年の各資格の合格率は、以下のとおりです。
- 一級建築士:9.9%
- 二級建築士:25.0%
- 木造建築士:35.5%
試験に合格するうえでは、主に以下の勉強方法があります。
- はじめに学科を集中的に勉強する
- 過去問を繰り返し解く
- 法令集と参考書を併用する
- 空き時間にアプリで勉強する
- モチベーション維持のために資格学校で勉強する
- 小さい目標を決めて計画的に勉強する
一級建築士と二級建築士については、過去の合格率や勉強方法について、それぞれ以下の記事に詳しくまとめています。
資格取得にあたって、ぜひ参考にしてください。
また、独立するには「管理建築士」の資格も必要です。
「管理建築士」とは、建築物の設計・施工・維持管理に関する専門的な知識と技術を持ち、建築物の適正な管理・維持・改修を行える資格のことです。
建築事務所には「1人以上の管理建築士を置かなければならない」という決まりがあります。
実際には、独立した建築士が管理建築士を兼ねるケースが多くなっています。
管理建築士になるには、建築士として3年以上の実務経験を積んだ後、管理建築士講習の受講が必要です。
実務を通じて人脈を広げる
企業勤めの建築士の間は実務経験を積むかたわら、積極的に人脈を広げていきましょう。
なぜなら、仕事で出会ったお客さんたちは、独立後のあなたのお客さん候補になるからです。
独立直後は実績がゼロのため、一から営業活動を頑張っても、なかなか仕事を受注できません。
しかし、会社員のときからお客さんと信頼関係を築けていれば、独立後に仕事がもらえる確立が高くなります。
独立に向けて資金を貯めておく
独立に備えて、今のうちから開業資金や当面の運転資金を蓄えておくのも重要です。
個人事業主として独立する場合、経営には主に以下のコストがかかります。
- 事務所の家賃
- 保険料
- 広告宣伝費
- 電話代
- 機材やソフトウェアなどの購入費用
- 交通費
- 営業費用
- 税金や社会保険料
運営に必要な経費を考慮すると、建築士として独立するのに500万円以上は必要と言われています。
独立に向けて、しっかり貯金しておきましょう。
関連資格を取得しておく
建築士と管理建築士だけでなく、関連する資格も取得しておけば、仕事の幅が広がり、独立した際に役立ちます。
建築士として独立する際に役立つ関連資格には、主に以下のようなものがあります。
| 資格名 | 持っていると役立つ理由 |
|---|---|
| 宅地建物取引士 | 宅地建物取引に関する知識や技能が求められることがあるため |
| 建築施工管理技士 | 設計から施工までの一連のプロセスを自身で担当する場合もあるため |
| 建築設備士 | 建築物の設備計画や設備設計に必要な知識が求められることがあるため |
| 安全衛生責任者 | 建設現場の安全管理を担当することもあるため |
これらの関連資格は、建築士として独立するうえで必須ではありません。
しかし、だからこそ、持っていれば優位な立場に立てるでしょう。
建築士事務所の登録を行う
独立の際には、建築士事務所の登録が必要です。
これを怠ると、懲役や罰金など刑罰の対象にもなるため、確実に済ませるようにしましょう。
登録は、保有資格に応じて、以下3つから選ぶ形になります。
- 一級建築士事務所
- 二級建築士事務所
- 木造建築士事務所
建築士事務所の登録は、オンラインでできます。
詳しい登録方法については、国土交通省の「建築士事務所登録のオンライン化について」に掲載されています。
建築士の独立についてのよくある質問
最後に、建築士の独立についてのよくある質問をまとめました。
よくある質問は、以下のとおりです。
- 建築士が独立するのに何年かかる?
- 建築士が独立する年齢は何歳くらい?
- 二級建築士でも独立できる?
各質問について、回答していきます。
建築士が独立するのに何年かかる?
大学で指定科目を修めて卒業した場合、一級建築士となって、最速で独立できるまでの期間は約5年間です。
この場合、卒業した年に一級建築士の試験が受けられます。
その後、2年以上の実務経験を積むことで一級建築士の免許登録が可能になります。
そこから、建築士として3年以上の実務経験を積めば管理建築士の資格を取得できるようになるので、最短5年間で独立できる計算です。
ただし、最短での独立はあまりおすすめできません。
建築士として独立し、成功するには、豊富な知識や高い技術力が不可欠です。
これらが不十分な状態で独立すると、失敗するリスクが高くなってしまいます。
そのため、条件を満たしていたとしても、独立までには5年より長い年月がかかると思っておいたほうがいいでしょう。
建築士が独立する年齢は何歳くらい?
建築士が独立する年齢は人によって異なりますが、一般的には経験を積んで技術を磨いた後、30代後半から40代前半が独立するタイミングとしてよく見られます。
もちろん、個人の事情や環境によって、それ以前やそれ以降に独立する場合もあります。
二級建築士でも独立できる?
二級建築士でも独立することは可能です。
ただし、二級建築士の場合、設計できる建物の規模に制限があります。
そのため、設計業務の拡大をする場合には、一級建築士の資格を取得する必要があります。
建築士として独立するなら数年単位の準備が必要
建築士として独立することのメリット・デメリットは、それぞれ以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・能力次第で会社員時代より高い年収が狙える ・仕事の自由度が高くなる | ・仕事が軌道に乗るまではかえって年収が下がる ・リスクがある独立に失敗するリスクがある |
建築士として独立すれば、能力次第で会社員時代よりずっと高い年収が狙える反面、仕事が軌道に乗るまではかえって年収が下がったり、事業に失敗して借金を負ったりしてしまうリスクもあります。
また、他の業種に比べても、建築士として独立するのには長い年月がかかります。
独立したいという方は、この期間にしっかり独立に向けた準備をしておきましょう。
独立に向けて、より高度な知識や技術力を身につけたいという方には転職がおすすめです。
全国に常時6,000件以上の案件があり、9割以上の方が年収アップにも成功している「施工管理求人サーチ」なら、あなたの希望条件に合った仕事がきっと見つかります。
ぜひ、求人をチェックしてみてください。
この記事をお読みの方におすすめの求人
株式会社夢真が運営する求人サイト「施工管理求人サーチ」の中から、この記事をお読みの方にぴったりの「最新の求人」をご紹介します。当サイトは転職者の9割が年収UPに成功!ぜひご覧ください。
大学卒業後、一級建築士となり、最短で独立するまでの期間は約5年間です。建築士の指定科目を修めて卒業した場合、その年に一級建築士の試験が受けられます。その後、2年以上の実務経験を積むことで一級建築士の免許登録が可能になります。そこから、建築士として3年以上の実務経験を積めば独立に必要な「管理建築士」の資格を取得できるようになるため、最短5年間で独立可能です。
施工管理の求人・転職情報を探すなら「施工管理求人サーチ」
当サイトで転職した人の9割が年収アップ。また、体力面やライフスタイルを考慮したキャリアチェンジも可能。業界トップの施工管理技術者:7,543人が所属する当サイトに登録して、転職活動を始めましょう。

当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。
おすすめ求人

編集部
建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。
株式会社夢真 コーポレートサイト

































