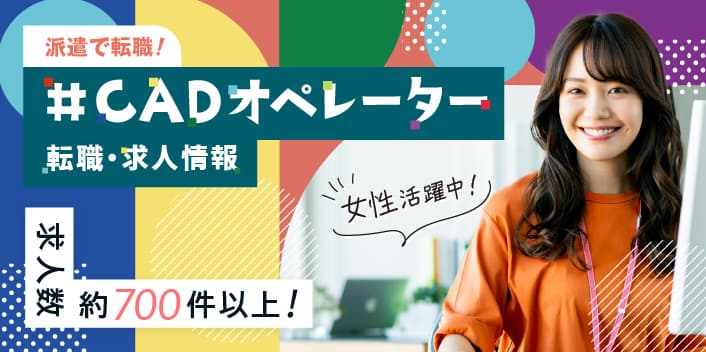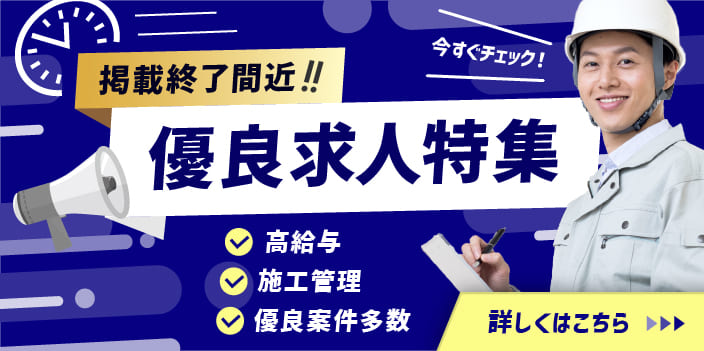基礎工事機械の転倒事故例5つ|施工管理時に確認するべき箇所とは?

最短30秒で予約!転職のプロに相談しよう
施工管理として今より良い条件で働きたい方は、夢真にお任せください!
目次
基礎工事機械とは
基礎工事機械は、自走して杭の打ち込みなどを行う大型の車両系建設機械です。
主な基礎工事機械は以下の通りです。
■基礎工事機械(例)
・パイルドライバー
・くい打ち機
・アースドリル
・リバースサーキュレーションドリル
基礎工事機械は地面に杭を埋め込んだり、高く持ち上げる作業のために使用されることが多く、高さが数十メートルになるものも珍しくありません。
そのため、バランスを崩しやすく、実際に基礎工事機械に関わる事故の多くは転倒が占めています。
基礎工事機械の転倒事故例5つ
実際に起こった基礎工事機械の転倒事故の事例を見ていきましょう。
1:くい打ち機が移動中に転倒
ある学校のプールの新築工事現場で、コンクリート杭を打設していたくい打ち機が移動中に転倒。なぎ倒された電柱が車を直撃し、2人が負傷しました。
原因は軟弱な地盤を敷板鉄なしで作業していたことにより、車体が地面にめり込んでバランスを崩したこととされています。この事故では現場責任者、オペレーターが責任を問われて書類送検されました。
基礎工事の現場において、表面は硬くても内部は緩い地面になっている箇所は少なくありません。重機移動の際には下部に一定規格の敷鉄板を敷いて施工の安全を確保することが重要です。
2:ワイヤーロープが過巻になり転倒
アースドリルのワイヤーロープが過巻になり転倒になった事故です。マンションの新築工事で、アースオーガーのエンジンをかけたままオペレーターが機械から降りて片付けをしていました。
この時、ブーム起伏レバーが「上げ」状態だったことと、安全装置の不良によってワイヤーロープが過巻になり転倒してしまいました。事故の原因は、エンジンを切らずに降車したことやレバーの確認が不徹底、安全装置の確認不足など複数あるとされています。
運転者の安全教育をしっかりと行う必要があるでしょう。
3:アースドリルの転倒
基礎工事機械のアースドリルの転倒でブームが道路を遮断し、歩行者らが6人負傷した事故です。ビルの新築工事現場で、前日打設した基礎抗の表層ケーシングをアースドリルで土中から抜き取るために、吊り上げる作業をしていたところ、アースドリルが転倒しました。
ブームが片側3車線の道路をふせぎ、アースドリル運転者、歩行者2人、トラック搭乗者3人の計6人が負傷しました。
用途外の使用が事故の原因でした。ただし、ブームについている補助吊り装置を使い限定的ですが、スタンドパイプやトレミー管などを吊り込む作業を行うことを認められています。
この事故では、補助吊り装置を使用による表層ケーシングの引き抜きするときの負荷が、制限荷重を超えため転倒しました。施工管理としては、揚重作業を移動式クレーンにて行うことで事故を防げるでしょう。
4:クローラーが沈下して転倒
基礎工事機械である、アースオーガーでPC杭の吊り込み作業中、転倒した事件です。クローラーが地面に沈下したことが原因でした。セメントミルク工法杭を施工中の鉄塔基礎工事現場で、地面が軟弱だったため、敷鉄板上でアースオーガーは作業を行っていました。
最後の杭を吊り込むため、およそ14m先から補助吊り装置のフックに、杭頭の玉掛けワイヤーロープを掛け巻き上げたところ、アースオーガーの右側クローラー前部の地盤が沈下し、後部が浮き上がりました。
運転者は操作を誤り、機体が鉄板から外れ、施工を行って埋戻した杭部分にめり込む形で横倒れとなり、運転者が下敷きとなる事故となりました。
敷鉄板からはみ出しがある状態で、アースオーガーが杭のつり込みを行ったのが原因です。また、敷鉄板上に残土が被ったため、敷鉄板の位置が確認できませんでした。さらに、施工管理上、作業計画の内容が不十分であったということも問題でした。

ゼネコンの求人、たくさんあります
業界最大級の求人数の中から、
年収にも働きやすさにもこだわった
「ゼネコン」の求人をどうぞ。
※転職成功率を上げたい人、コンサルタントに最適な求人を紹介してほしい人は2件以上の応募がおすすめです!
5:くい打ち機が民家を直撃
基礎工事機械である、くい打ち機が、軟弱地盤を敷鉄板なしで移動中に転倒した事故です。
高校のプールを新築工事する現場で、コンクリート杭(直径45cm、長さ16m)をくい打ち機で打設していました。
102本のうち前日までに70本を終了し、当日は3本目を打設した後、次の打設位置まで移動中に地面に左のクローラーがめり込み転倒しました。電柱とブロック塀をなぎ倒し、道路を横断して向い側の敷地に倒れたというものです。
なぎ倒された電柱が車を直撃し2人が負傷しました。現場内には敷鉄板を5枚敷いていたものの、転倒事故を起こした場所には敷いていませんでした。
施工管理時に事故を防ぐための確認

施工管理は「原価管理」「品質管理」「工程管理」「安全管理」の4つの管理の総称です。安全管理は建設現場で、安全な作業環境を整備することです。
施工管理者は、事故が起こることを想定して安全対策を施すこと、季節や天候などの環境により変化する危険性の予測を行うことが必要です。
さらに施工管理の中で、施工中の状況変化による事故の予測など、常に状況が変化する中でも、建設現場で安全を保持する対策を求められています。
施工地盤のリスクについて
建物の建築では、基礎工事を行う地質や地盤をそのまま、または整地等で改変することで機能を維持しています。そのように考えると、地質や地盤は、建物にとって重要な存在といえます。
盛土などを除くと、地質や地盤は自然に形成されたものであり、建築物建造の際のリスクとなり得ます。地質や地盤は不確実性が大きいこと、不確実性が施工に大きなリスクを与えることを、施工管理者はあらかじめ認識しておく必要があります。
作業上のリスクについて
建築現場の作業では、足場からの落下、基礎工事機械の取り扱い事故、クレーンからの重量物の落下などが挙げられ、施工管理者はこれらの安全管理に気を付ける必要があります。
吊り荷下の人払いは、吊り荷の落下事故を防ぐために必要なことですし、高所作業時に安全帯を使用することの徹底は、足場からの転落時の命綱として必要なことです。
施工管理の立場から、このような安全管理を現場の全員に徹底することが重要です。事故を未然に防ぐことが、施工管理者にとって重要な任務です。
運転を安全に行っているか
基礎工事機械の運転を乱暴に行うのは厳禁です。特に吊り荷中の移動は、慎重に行う必要があります。旋回時には杭打ち機の重心移動や、リーダーなどの傾きでバランスを崩しやすく、特に注意が必要です。
用途外利用は特に大事故の原因となる行為であるので、施工管理者は安全管理上行ってはいけないことです。また、杭打ち機の移動時の転倒事故も多いので、施工管理上、注意が必要なものです。
風のリスクを考慮しているか
基礎工事機械の運転では、風のリスクに注意が必要です。風の圧力は風速の2乗に比例しますので、風速が2倍になれば、吊り荷におよそ4倍の風圧がかかることになります。
施工管理上は、吹き流しの設置を行うことで、風向きと風速を現場で判断できます。さらに風速計を設置し、運転者が強い風を判断できるようにするとよいでしょう。
強風時はクレーン作業は禁止となりますが、地表よりも高いところの方が風速が早いということに気を付ける必要があります。
施工管理を徹底し基礎工事機械による事故を減らそう
今回紹介した事例以外にも、基礎工事機械の転倒による事故が発生しており、時には複数の死傷者が出るケースもあります。事故が発生したら、現場責任者である施行管理者が罪を負わなければならないことも考えられます。
悲惨な事故を回避するためにも、オペレーターや作業員の安全教育、特別仕様書を正しく作成するように心がけましょう。
関連記事:
施工管理者なら覚えておくべき重機の車両系建設機械運転技能講習:基礎工事用
施工管理者なら覚えておくべき重機の車両系建設機械運転技能講習:整地・運搬・積込み用及び掘削
施工管理なら知っておきたい!建設現場で活用する重機の故障・修理箇所:ダンプカー
当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。
おすすめ求人

編集部
建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。
株式会社夢真 コーポレートサイト