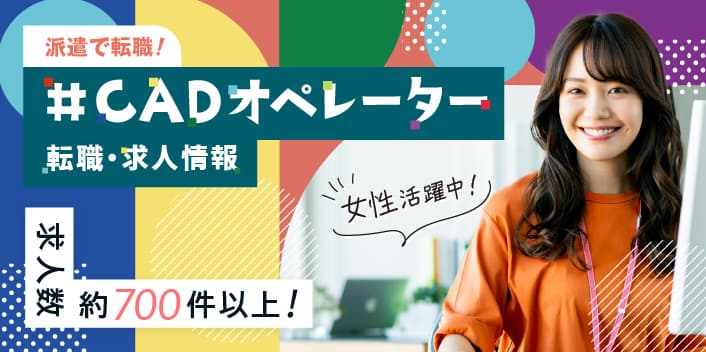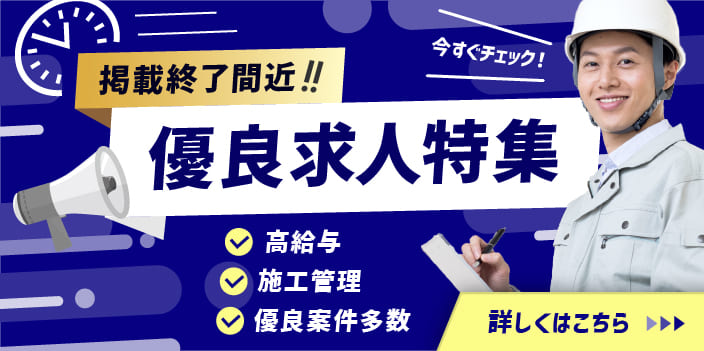建築士の転職には二級取得がおすすめ!資格を取るメリットやその他の種類も紹介


最短30秒で予約!転職のプロに相談しよう
今よりもっと良い条件で働きたい方は当サイトにお任せください!
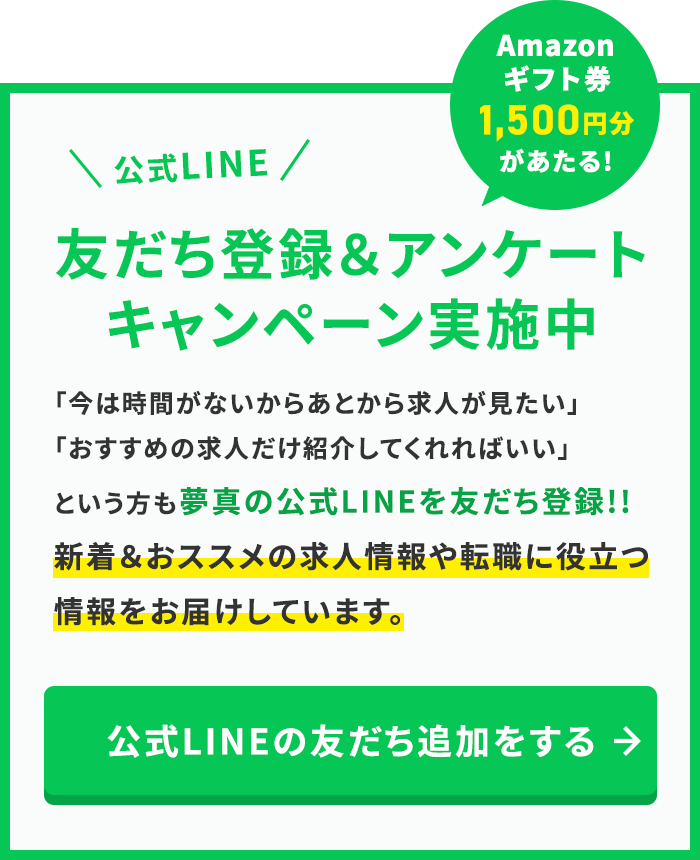
目次
建築士の3つの種類
建築士とは、建築法に則って定められた資格です。建築士には「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」があり、それぞれの資格によって設計、工事監理できる建築物の規模や業務範囲に違いがあります。
ここで、その3つの建築士資格について詳しく解説します。
出典:建築士の種類と業務範囲|公益財団法人建築技術教育普及センター
1:一級建築士
一級建築士は建造物の大きさや用途に関わらず、全ての建築物の設計と工事監理を行うことができます。そこには木造建築物も含まれ、個人から受注する戸建ての住宅から、国家規模のスタジアム建設まで、建物の規模に制限なく設計できます。
一級建築士の資格は、転職の際の採用条件に記載されていることも多く、取得するメリットがある資格だと言えるでしょう。
2:二級建築士
二級建築士は、戸建ての家のような比較的小さな建築物について設計・工事監理をします。
木造建築物の場合なら建物の高さ13m、軒の高さ9mで延べ面積1000㎡のものが対象です。木造以外の建築物の場合は、同じ高さ制限に加え、延べ面積が300㎡とされるなど、さらに厳しい制限がかかります。
転職の際の採用基準は、二級建築士以上の資格が求められることが多く、一級建築士と同じく大きなメリットがある資格です。
出典:建築士の種類別の業務範囲|公益財団法人建築技術教育普及センター
3:木造建築士
木造建築士は、より小規模な木造建築物の施工・工事監理を行います。
延べ面積300㎡以下、2階建までの木造建築物に携われるのが木造建築士ですが、木造に特化したスペシャリストとして、木造建築の多い日本では有効な資格です。二級建築士へのステップとして取得されることも多くあります。
出典:建築士の種類別の業務範囲|公益財団法人建築技術教育普及センター
建築士3種類の平均年収
取得した資格によって、仕事の規模が異なる建築士ですが、平均年収はどれほど違うのでしょうか。それぞれの平均年収と、年収を上げるための方法などを紹介します。自分のキャリアプランや障害設計と合わせて、どの資格を目指すのか考えてみてください。
一級建築士の平均年収
厚生労働省が発表した「平成29年賃金構造基本統計調査」によると、小中規模の事業所に所属する一級建築士の平均年収は約700〜750万円となっています。
1,000人以上の大規模な事業所に所属している一級建築士の平均年収は900万円を超えています。ただし、この統計調査による対象の平均年齢が40代半ばであるため、役職に就いているからこその年収だと考えた方がよいでしょう。
二級建築士の平均年収
戸建て建築の設計・工事監理を行う二級建築士は、ハウスメーカーや工務店、設計事務所などに活躍の場があります。
現場に出て工事監理の仕事のみをする場合と、ハウスメーカーなどで営業や企画の仕事と兼務をする場合は、後者の方が年収が高い傾向です。
二級建築士の平均年収は420万円程度と言われています。しかしハウスメーカーでの営業ではインセンティブが月給に上乗せされることが多いので、メインとしている職種や勤務する会社の形態で大きな開きがあります。
木造建築士の平均年収
木造建築のスペシャリストとしての資格が木造建築士ですが、その年収は一級建築士や二級建築士に比べると低めです。比較的小さな住宅などの木造建築物を担当するため、1人で担当する作業量が多い側面もあります。
厚生労働省が発表した職業情報提供サイト(日本版O-NET)によると、木造建築士の資格保有者が多い大工の平均年収は377.7万円ほどとされています。
出典:職業情報提供サイト(日本版O-NET)大工|厚生労働省
二級建築士の仕事内容とは

二級建築士は、戸建て住宅の設計・工事監理する仕事が主になります。一級建築士と比べて施工規模には制限がありますが、その一方で戸建て住宅の設計に特化するなど、より専門的で顧客に寄り添った仕事ができるメリットがあります。
ここでは二級建築士の仕事内容を紹介します。
建物の設計や設計の監理
二級建築士の主な仕事は戸建て住宅の設計と工事監理です。戸建て住宅の場合は、施主である個人顧客と向き合い、住宅の希望や実用性に沿った設計を行います。
また、建築や土木の知識を持った二級建築士が設計の監理をすることで、安全性も備えた建築が可能になります。
施工の管理
建築現場では、設計をした二級建築士や、その他の現場監督資格を持った人が多くの職人を監督し、指示を出す役目をします。
設計図通りに施工が進んでいるのかや、職人たちが安全に作業するための環境が整っているのかも、二級建築士が確認するべき大切な仕事です。
二級建築士の資格を取るメリット9つ
二級建築士は、木造建築士よりも建築施工の規模に制限は受けないものの、一級建築士よりは小さな建築物に関わることになります。
木造建築士や一級建築士などの資格がある中で、二級建築士の資格を取るメリットとは何でしょうか。ここで、二級建築士の資格を取るメリットを9つ紹介します。
- 顧客の信用を得られる
- 転職に有利
- 資格手当がある
- 優良な企業からの内定をもらいやすい
- 建築士としてのキャリアを支えてくれる
- 昇格に有利になる
- 一級建築士取得試験の受験資格をもらえる
- 学歴に関係なく評価される
- 技術職として公務員への道もひらける
1:顧客の信用を得られる
二級建築士の仕事の大半は、戸建て住宅の設計・建築です。ハウスメーカーや工務店などでは営業や管理の仕事を兼務することも多くありますが、その際に顧客に差し出す名刺に二級建築士の資格が記載されていると、顧客からの信頼度が上がります。
営業担当者として、二級建築士の資格を名刺に記載することは、顧客とその信頼を得られる大きなメリットです。
2:転職に有利
住宅販売や住宅リフォームの業界においては、二級建築士の資格を保有している人材は需要があります。
高齢化社会に伴って、住まいをバリアフリーにリフォームしたり、将来を見越した平屋建築なども年々人気が高まっています。
住居建築を知り尽くした二級建築士は、建築商材のメーカーや販売会社にとってもメリットがある人材のため、転職の際には非常に有利な資格です。
3:資格手当がある
二級建築士は難易度の高い資格のため、資格を持っている人に毎月の給与に上乗せする形で資格手当を出す企業は少なくありません。資格保持者にとって嬉しい制度ですが、企業にとっても二級建築士が在籍していることはメリットであるため、資格手当が出されます。
4:優良な企業からの内定をもらいやすい
大きなハウスメーカーや大手ゼネコンなどは、二級建築士以上の資格を採用基準にしています。
不動産販売会社や住宅リフォーム会社のようなその他の企業でも、資格取得者が多くいることで、企業のイメージアップにも繋がることから、応募条件に必須とされていたり、審査の際に優遇されたりします。
二級建築士という形になった資格を持つメリットは、就職や転職の際に自分のスキルや努力を証明できることでもあります。
5:建築士としてのキャリアを支えてくれる
二級建築士は、戸建て住宅のメーカーや設計事務所、工務店などで喜ばれる資格です。そこでは建築士としての仕事のみならず、営業やデザインなどの幅広い職務に携わる機会があります。
現場監理を突き詰めて一級建築士を目指したり、住宅建築のプロフェッショナルとして顧客と向き合ったりなど、転職を含めた様々なキャリアプランを描けるのも二級建築士のメリットです。
6:昇格に有利になる
二級建築士は、建築士としての仕事をしながら、営業などの職務を兼務する機会も多いため、建築士のキャリアを積みながら営業スキルや販売スキルなどを磨くことで、昇格の道を開けやすくなります。
一つのことだけに集中するのではなく、幅広い視野でスキルアップやキャリアアップを目指せるのも、二級建築士のメリットです。
7:一級建築士取得試験の受験資格をもらえる
令和2年に建築士法が改正され、一級建築士の受験資格が大幅に緩和されました。この改正で、二級建築士の資格を取得すれば、実務経験を問わず、すぐに一級建築士の受験資格をを付与されることになりました。
一級建築士試験に合格してから4年の実務経験を積むことで、一級建築士の免許登録が可能です。従来、受験資格に必要だった実務経験が、試験合格後の免許登録までの条件に置き換わった形です。
出典:報道・広報|国土交通省
8:学歴に関係なく評価される
二級建築士の受験資格は、学歴によって実務経験が課されたり課されなかったりバラバラです。
高校や高等専門学校、大学の指定科目を修めて卒業した場合はすぐに受験可能ですが、中卒の場合は実務経験が7年必要とされています。
スタート地点がどうであれ、建築士の資格を取るには、難易度の高い試験を突破するほどの努力と実力があるのですから、二級建築士の資格があれば学歴に関係なく評価されます。
出典:令和3年 二級建築士試験 木造建築士試験 受験要領|公益財団法人建築技術教育普及センター
9:技術職として公務員への道もひらける
新卒として公務員の建築へ採用されるには、建築士の資格は必要ありません。しかし、中途採用として公務員の技術職へ転職するには、応募条件の中に一級もしくは二級の建築士資格が書かれていることがほとんどです。
公務員としての仕事では、街づくり計画や建築物の許可・指導など、民間の企業とはまた違った仕事の形が多くあります。
二級建築士の資格が活きる転職先9つ
二級建築士の資格が求められるのは、設計や建築の現場だけではありません。
ここでは、二級建築士の資格が活きるおすすめの転職先を9つ紹介します。資格取得後に、どのような職務に就けるのかや、どこに需要があるのかなどを知ることで、キャリアプランニングをすることができます。
- 建築資材の商社
- 不動産販売会社
- 不動産管理会社
- 住宅設備機器の商社
- 行政書士
- 設備工事会社
- 役所の建築課
- メンテナンス関連の会社
- リフォーム関連の会社
1:建築資材の商社
二級建築士の資格は、建築資材の商社でも非常に役立つものです。木材や建築資材に関する知識が豊富な二級建築士は、実際の建築現場に関わることが少なくても、施主の要望にそった建築資材を紹介したり、営業やアドバイスを行ったりします。

ゼネコンの求人、たくさんあります
業界最大級の求人数の中から、
年収にも働きやすさにもこだわった
「ゼネコン」の求人をどうぞ。
※転職成功率を上げたい人、コンサルタントに最適な求人を紹介してほしい人は2件以上の応募がおすすめです!
建築資材の商社は大手メーカーであることが多いため、福利厚生などのメリットも期待できます。
2:不動産販売会社
不動産販売会社は、土地とともに建物の取り扱いも行うため、ここでも二級建築士の資格が役立ちます。
転職サイトなどで不動産販売会社の求人情報を見てみると、二級建築士以上の資格取得が必須であることが少なくありません。このことから、二級建築士の資格は建物を作ることから販売することまで、広範囲で有効なメリットのある資格だと言えます。
3:不動産管理会社
不動産管理会社への転職も、不動産販売会社と同様、二級建築士以上の資格が採用試験の応募条件になっていることがほとんどです。
不動産業界においても、建築物のプロである建築士の需要は高まる一方です。顧客の不動産に関してアドバイスをしたり、正確な鑑定をしたりなど、不動産管理会社にとっても顧客にとっても重要なポジションになるのが建築士です。
4:住宅設備機器の商社
二級建築士は、その資格で許可されている建築物の大きさ制限により、戸建て住宅を手がけることがほとんどです。顧客と直に向き合うことも多くあり、自委託設備における顧客のニーズや流行などにも敏感です。
そのため住宅設備機器の商社では、それぞれの住宅に合わせた住宅設備を提案できるなど、豊富な知識と経験を備えた二級建築士は重宝される傾向にあります。
5:行政書士
行政書士は、法律系国家資格の登竜門です。官公庁に提出する書類や事実証明・権利義務に関する書類作成を、個人もしくは企業に代わって行います。
行政書士や建築士は、ダブルライセンスを取得している人も多く存在します。建築士としての知識と経験を持った行政書士なら、住居賃貸権や許認可申請などの契約書・申請書の作成や手続き代行などに力を発揮できます。
6:設備工事会社
設備工事会社では、配管空調設備や電気設備などの設計・工事を行っています。室内環境を整えたり、エネルギーを効率よく利用したりなど、快適な住まいや建物に重要な仕事を担います。
住居における建築設計のプロとして二級建築士は重要な存在であり、その知識とスキルは設備設計作業の大きな力です。
設備設計のスペシャリストである「設備設計一級建築士」は、一級建築士資格が受験資格です。二級建築士から徐々にステップアップしていくのもキャリアアップのモチベーションに繋がります。
出典:設備設計一級建築士講習|公益財団法人建築技術教育普及センター
7:役所の建築課
地方の役所の建築課では、建築基準法に基づいた建築指導や公共工事による建設・街づくり、市営住宅の管理・修繕などを行っています。
公務員ということもあり、充実した休日・休暇制度や、高給ではなくとも安定した収入が見込めることが大きなメリットです。
公務員になるためには、各自治体が課している地方公務員試験に受かる必要があります。受験には年齢制限がある自治体がほとんどです。公務員への転職を狙うなら、年齢制限に引っかかる前にキャリア設計をしておきましょう。
8:メンテナンス関連の会社
建物を引き渡した後でも、その建物の快適性や安全性などを保持するためのメンテナンスは欠かせません。
戸建て住宅の場合は、水回りや床下、外構などが定期的なメンテナンスが必要な部分です。転職市場では、ビル管理・メンテナンスなどの求人でも、建築士は有効な資格とされています。
公共建築物の定期検査・定期点検をする資格があるのも、二級以上の建築士または建築設備検査資格者です。
9:リフォーム関連の会社
中古物件を購入して理想の住宅にリフォームしたり、老後に備えてリノベーションしたりする人が増えています。
ハウスメーカーでリフォーム事業に取り組む企業も増えていますが、大半のところが自社物件のみの取り扱いです。そんな中でリフォーム専門会社の数と実績が増え続けています。
住宅の改築や増築が適切な書類申請をするべきものかの知識や、リフォームプランの設計と監理などは建築士の資格が有効です。大幅な住宅改築などの場合は、リノベーションと言われることもあります。
建築士の働き方の種類は?

建築士は高度や技術と知識を備えた資格者で、多くの場合は、ハウスメーカーや工務店、設計事務所などで正社員で雇用されています。ある程度キャリアと詰んだ場合は、独立開業して経営者となる人もいます。
また、自身の都合や家庭の事情のために一度正社員を辞めた人が、正社員としての転職ではなく、派遣社員として働くこともあります。建築業界に特化した派遣会社もあり、一級もしくは二級の建築士資格があれば、優遇されることがほとんどです。
育児や介護などをしながら、アルバイトやパートの形態で事務作業や図面チェックを行ったり、在宅で副業を行ったりする働き方もあります。
建築士の資格3種類の概要
建築士には、国家資格である一級建築士と、都道府県から資格認可を得る二級建築士・木造建築士があります。
一級建築士は二級建築士や木造建築士と違い、請け負える建築工事の規模に制限はなく、転職市場では強みがあります。
しかし、一級建築士はその建築規模の大きさから、比較小さな戸建て住宅などには関わりが少なく、戸建てや木造住宅においては二級建築士や木造建築士の方に経験としての強みがあります。
ここからは、それぞれの建築士の資格を取るのに必要な試験について説明します。
1:一級建築士
一級建築士は、設計する建物の高さや広さに制限がないことから、戸建て住宅からスタジアムやアリーナのような大きな建築物の設計を行えます。
建築士の中で唯一の国家資格で、設計・構造・設備など、全てにおいて高度な知識が必要になります。転職市場においても、一級建築士取得は大きな武器です。
構造/設備設計一級建築士講習などは、一級建築士の資格取得が受講資格となっています。
出典:令和3年一級建築士試験受験要領|公益財団法人建築技術教育普及センター
受験料・試験内容
令和3年の試験から、インターネットによる申込が原則となりました。
一級建築士試験は17,000円で、他に事務手数料が必要です。支払いは申込時に、指定するクレジットカード、またはコンビニエンスストア決済のどちらかが選択できます。
試験は「学科の試験」と「設計製図の試験」があり、「学科の試験」に合格しないと「設計製図の試験」は受験できません。
「学科の試験」では、「計画」「環境・設備」「法規」「構造」「施工」の5科目が四肢択一式で出題されます。「設計製図の試験」では、あらかじめ公表されら課題の建築物の設計製図を行います。「設計製図の試験」はこれだけで6時間30分の試験時間とされています。
受験資格
一級建築士の受験資格を有するのは「大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等において指定科目を修めて卒業した者」「二級建築士」「建築設備士」、そしてその他国土交通大臣が特に認める者(外国大学を卒業した者等)と規定されています。
資格試験に合格してからも、免許登録要件には実務経験が必要で、大卒で2年以上、高専卒で4年以上、二級建築士で二級建築士として4年以上となっています。
2:二級建築士
二級建築士は、一級建築士に比べて設計できる建築物の大きさに制限がありますが、戸建て住宅などのような個人の顧客に需要がある仕事です。
都道府県から資格認可を得られる二級建築士は、資格取得後すぐに一級建築士の資格試験に臨むことができます。
二級建築士は転職にも強く、建築業界のみならず、建築資材の商社や不動産関連業界からも欲しがられる人材です。
出典:令和3年 二級建築士試験 木造建築士試験 受験要領|公益財団法人建築技術教育普及センター
受験料・試験内容
二級建築士試験の受験料は18,500円で、他に事務手数料が必要です。
試験は「建築計画」「建築法規」「建築構造」「建築施工」の4つの学科試験と、設計製図の試験で構成されます。学科試験に合格しないと、その後の設計製図の試験は受けられません。
設計製図の試験時間は5時間で、一級建築士試験よりは短いとは言え長丁場のため、かなりの集中力と忍耐力が求められます。
受験資格
受験資格は、大学・短期大学・高等専門学校・高等学校で指定の科目を修めて卒業した人、または実務経験7年の人、都道府県知事が同等と認める人です。
都道府県知事が同等と認める人とは、外国の大学等を卒業し受験を希望した人などのことで、所定の資料を提出する必要があります。
資格合格後の免許登録は、大学・短期大学高等専門学校卒業の場合は実務経験なしで行えます。高等学校卒業の場合は2年の実務経験が必要です。
3:木造建築士
近年、エコ意識の高まりや天然木材を使用した自然派の住まいとして木造住宅が人気です。木造建築士は、木造住宅のスペシャリストとして、建築現場においても、建築木材の営業においても需要があります。
木造住宅に特化し、木造建築物の構造や知識に深い知見のある木造建築士は、転職市場でも強い資格です。
出典:令和3年 二級建築士試験 木造建築士試験 受験要領|公益財団法人建築技術教育普及センター
受験料・試験内容
木造建築士の受験料は二級建築士と同じく、18,500円と別途事務手数料です。
試験科目も二級建築士と同じように「建築計画」「建築法規」「建築構造」「建築施工」の4つの学科試験と、設計製図の試験で構成されます。設計製図の試験では、令和2年から過去5年は、木造2階建ての専用住宅が課題とされています。
受験資格
木造建築士の受験資格も二級建築士と同じです。大学・短期大学・高等専門学校・高等学校で指定の科目を修めて卒業した人、または実務経験7年の人、都道府県知事が同等と認める人が受験可能です。
資格取得後の免許登録要件も二級建築士と同じく、大学・短期大学・高等専門学校卒業の人は実務経験なし、高等学校卒業の人は2年以上、実務経験7年で受験資格を得た人はさらに7年以上の実務経験とされています。
公益財団法人建築技術教育普及センターが発表した令和3年の試験合格者の主な属性は約90%が大学院生を含む学生もしくは研究生でした。
様々な建築士の働き方を検討しよう
二級建築士の資格を主に、3つの建築士資格とその可能性を紹介しました。
建築士は建築物の設計・工事監理に関わることから、その後のメンテナンスやリフォーム、不動産監理や住宅設備に役立つ知識まで備えています。これは転職を考えた時にも大きな武器になり、様々な職種や働き方の選択肢を得られることに繋がります。
ぜひ二級建築士の資格取得を目指し、自分にあった働き方を見つけてください。
当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。
おすすめ求人

編集部
建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。
株式会社夢真 コーポレートサイト